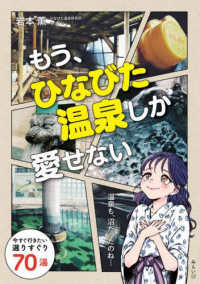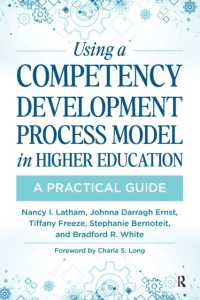目次
第1章 一斉授業をつくる10の原理(ゴールイメージの原理;フレームワークの原理;メインターゲットの原理;ユニットプログラムの原理;ブリーフィングマネジメントの原理 ほか)
第2章 一斉授業をつくる100の原則(基本として身につけたい10の原則;市導言を機能させる10の原則;机間指導を機能させる10の原則;発言指導を機能させる10の原則;小集団交流を機能させる10の原則 ほか)
著者等紹介
堀裕嗣[ホリヒロツグ]
北海道教育大学札幌・岩見沢校修士課程・国語科教育専修修了。現在札幌市立北白石中学校教諭。「教師力BRUSH‐UPセミナー」「研究集団ことのは」代表、「実践研究水倫」研究担当を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
8
アクティブラーニングの導入が進められる一方で、一斉授業を疎かにしてはいけないと思い読む。すでに実践できているものもあれば、頭ではわかっていても実践できていないものもある。著者の言う「攻めの質問」と「受けの質問」で自分は重点が「受け」側に偏っていると自覚した。だいぶ業務に慣れてきたので、事前の授業準備の時間をもう少し増やして説明・質問の流れの想定をより具体化していきたいと思った。2021/04/11
しんえい
3
自分は授業の構造を今一度考え直すべき。生徒達自信が課題発見・解決を自分たちでできるようにする授業をできているか?1時間単位でしか授業を構想できていないのではないか?単元間のつながりや1年間の見通し、3年後のゴールイメージを具体的に考えなければならない。その授業が知識指導型なのか体験型なのかをイメージし、そこから帰納型か演繹型なのかを決定する。生徒達に相互評価させながら、到達度を自覚させる。説明と発問と指示を明確に分ける。2020/09/19
しんえい
3
授業中に意識しなければいけないこととして、なんとなく経験的にわかっていたことを完璧に言語化してくれている。評価評定を機能させる原則、授業構成の原則が特に勉強になった。授業構成は単元間やカリキュラム等の「横」も意識しなければならない。2019/07/09
草食系教師
2
一斉授業、昨今では否定的な意味で使われることが多い。しかし、「一斉授業」をできない教師に、「協同学習」や「ファシリテーション」は成立させられないという主張のもと、様々な原理・原則が語られる。堀氏のどの著書においてもこの原理原則が貫かれており、一貫性を感じる。本書も非常に具体的で私は納得する部分が大きかった。まずは、全ての時間にグループワークを取り入れることから実践している。2021/09/20
gongon
2
今回は、「説明」に関しての学びが多かった。ブログに記載しています。http://threepocari.hatenablog.com/entry/2018/01/03/2235162018/01/04