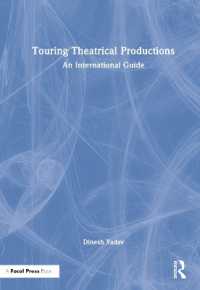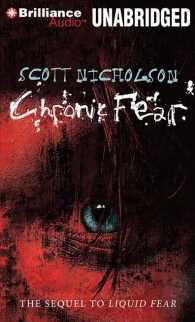内容説明
公共空間の過度な活性化でまちは窮屈になっていない?ルールに縛られた空間を解きほぐし公民連携の課題を解決する、アクティビティ+マネジメント実践集!
目次
1 もっと私的に自由にまちを使おう(私的で自由な行為がつくるまちの風景;窮屈でシステム化された都市生活 ほか)
2 PUBLIC HACKを体現する実践者たち(アーバン・アウトドアを堪能する;常識から解き放たれる ほか)
3 PUBLIC HACKが持続するためのコツ(そんなこと本当にできるの?;都市生活の可動域を広げるために ほか)
4 利用者の自由を広げるマネジメント(公民連携が抱える構造的課題;これからの公共空間マネジメント ほか)
5 PUBLIC HACKがまちの価値を高める(まちの自由度の高さが生みだす効果;スキマはまちの自由度を測るモノサシ ほか)
著者等紹介
笹尾和宏[ササオカズヒロ]
水辺のまち再生プロジェクト事務局。1981年大阪生まれ。大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻、経済学研究科経営学専攻修了。ともに修士。2005年から水辺のまち再生プロジェクトに参画し、2007年株式会社大林組に入社、不動産開発・コンサルティングに従事。2015~2018年に出向、エリアマネジメントに従事。現在は育児のため休職中(2019年時点)。2017年よりNPO法人とんがるちから研究所研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
makoto018
9
public hackとは、公共空間を私的に自由に使うことでまちを楽しむこと。水辺ダイナー、流しのこたつ、芝生シアター、大阪ラブボート。事例を読むだけで楽しくなるけど、規制や苦情は大丈夫と思ってしまう。すると、Chapter3で、法令をよく調べて理解すること 、周囲への気くばりについて解説してある。Chapter4は、公民連携がまちの自由度を下げないようにするにはという話でここもなかなかよい。個人の満足感がまちへの満足度を上げ、それがシビックプライドに繋がり、その連鎖が、面白いまちを作るという論には納得。2020/03/24
なりぶぅ
3
『パブリックハック』という耳慣れない言葉。確かに公共空間を皆が思いのままに使えて楽しむことが出来れば、自由度は格段に上がるけれど現状は難しそう。私自身、一般的ではない異質な行為に対して通報はしないまでも受け入れ難いことはままあるし、受け身でいる方が楽だと思ってしまっている。使う側も「行儀よく丁寧に振る舞う」ことや他の人に「不公平感、疎外感を抱かせない」ことが必要。要は使う側の配慮と見る側の寛容性を持ち合わせて、互いに歩み寄ることが大事ってことかしら。2021/10/10
takao
3
・これはいい。都市生活のアウトドアーでの新たな楽しみ方2020/03/01
hukukozy
3
昨今,数多く見られる公園などでの「禁止事項の増加」など,公共空間での活発なアクティビティは妨げられている.これらは社会の効率化・合理化による「思考停止」が原因だとし,誰でも簡単に始められる「まちを私的に自由に使う方法(=PUBLIC HACK)」を紹介.「チェアリング」や「青空カラオケ」のような具体的な事例を挙げつつ,それらが法律的に何ら問題ないホワイトな行為だというフォローも.まちは人びとの生活によって成立しており,そして,まちは解像度を上げることであり方がまったく変わるということを気づかせてくれる.2019/10/08
Monty
2
もっと早く読むべきだったと後悔。まちづくりに関わる従事者として、市井の市民として、個人として、まちに出たくなるし、使いたくなる。何をやるにしても消費者というライフスタイルはつまらない、と決意を新たに明日を迎えよう。素晴らしい読書体験 2025/05/21
-
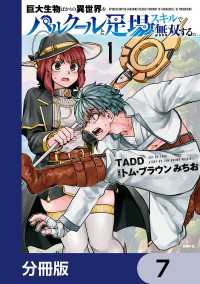
- 電子書籍
- 巨大生物ばかりの異世界をパルクールと足…