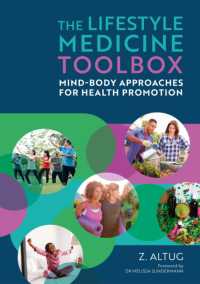内容説明
歌舞伎は日本文化のスープである。役者にぞっこんはまったり、上手い!下手くそ!と叫んだり、魅力があると喜んだり、魅力なしと声高に罵ったり、笑ったり、涙ぐんだり…そしてちょっといい気分に、生きているのが少し楽しいと思えるようになる。
目次
序幕 生きているのが少し楽しくなる
第1幕 歌舞伎を一度は見なくては
第2幕 来月、行くことになった
第3幕 歌舞伎見物の日が来た
第4幕 幕が開いた
第5幕 幕が閉まった
第6幕 歌舞伎見物が終わった
第7幕 歌舞伎の三つの謎―よくある質問
第8幕 伝統とは何か
終幕 歌舞伎の魅力にずぶずぶ溺れてください
著者等紹介
船曳建夫[フナビキタケオ]
1948年、東京生まれ。東京大学名誉教授・文化人類学者。フィールドワークをメラネシア(バヌアツ、パプアニューギニア)、ポリネシア(ハワイ、タヒチ)、日本(山形県)、東アジア(中国、韓国)で行う。その他にも世界各所を探訪している。専門の関心は、人間の自然性と文化性、儀礼と演劇の表現と仕組み、「日本」とはなにか。「アーツカウンシル東京」で東京の芸術文化創造に参画(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヒデミン@もも
49
東大の名誉教授で結構な年齢の方なのに文章がすっごく解りやすい←偏見ですね(失礼)。 歌舞伎に行きたくなること間違いない。初めて歌舞伎を観たのは坂東玉三郎様。それ以来数えられるほどしか行けてないけど、いつか着物来て行きたい。それにしても東京でこんなに歌舞伎が演じられてる劇場があったとは知らなかった。そして十五代目市村羽左衛門ひと目お会いしたかった。2017/02/18
m
7
前半はさくさく、後半はペースダウン。東大の教授だから難しいことを書いてるのかと思いきや、初心者向けだからか分かりやすい。この間は愛之助を見たので、今度は海老蔵を見に行こう。2017/06/01
KUMYAM@ミステリーとSF推し
6
歌舞伎座に行くのにようやく身構えなくてもよくなってきたところで、改めて初心にかえった気分。次に行くのがますます楽しみ。▼とは言え、知ってることばかりかな~とあまり期待もしてなかったのに、「第八幕 伝統とは何か」で大きな収穫があった。着物のこと、翻訳小説のこと、それぞれに当てはめて思うところがいろいろと。2019/04/28
きみー
6
他にいくつか読んだ歌舞伎入門書よりも、比較的とっかかりやすいと感じました。「一度は見てみようかな?」という人を対象にしているため、ややこしいこと、何度か行くと分かることはある程度端折っているからでしょうか。しかし、最後のかぶきとは?や歌舞伎を守らなければならない理由などは、少し筆者の想いが強く、「そこまでか?」と思ってしまう部分があります。何はともあれ、日本独特に発展した舞台芸能として、楽しんでみることは悪くない、と思わせてくれます。2017/01/22
氷柱
4
646作目。11月29日から。歌舞伎に行きたくなるような一作・・・ではない。歌舞伎大好きおじさんの自分語り感が凄まじいけれど、そういうものとして受け止めるとそれなりに好感を持つことができる。終盤に出て来る小難しい話は作者が学者であることを思い出させる。しかし基本的には平易な文章で率直に記されているので歌舞伎大好きおじさんの存在をこれでもかというくらい満喫することができる。特に序盤のゆるっとした感じが最後まで続く辺りが作品のイメージを強調している。歌舞伎大好きおじさんの御姿を拝もう。2020/11/30
-
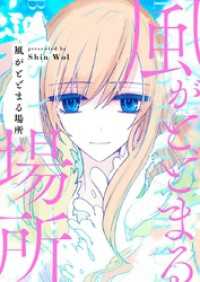
- 電子書籍
- 風がとどまる場所【タテヨミ】第8話 p…