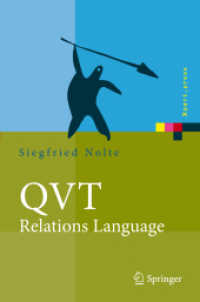内容説明
わたしたち人間だけがことばを自在に操ります。ひとのことばの本質的特徴とは何であり、動物のことばとどう違うのでしょうか。そして、人類は、そのことばをいつ、どのようにして獲得したのでしょうか。言語学の視点をベースにしながら、最近めざましい発展を遂げている言語の起源・進化研究の学際的知見を駆使して、それらをやわらかい語り口と平易な文章で解き明かそうというのが本書のねらいです。
目次
第1部 ひとのことば(ひとのことばとは;私たちの日本語のことばの知識;ひとに共通のことばの知識)
第2部 ひとのことばの起源と進化(ことばの起源と進化;進化論をめぐって;ひとの進化と脳の進化;ことばの起源と進化は二段階で;ことばの「化石」;ことばはコミュニケーションのためならず;ことばなコミュニケーション用に作られているのだろうか;単語が消える(?)
明日に架ける)
著者等紹介
池内正幸[イケウチマサユキ]
1949年新潟県上越市(旧高田市)生まれ。東京教育大学大学院博士課程英語学専攻単位取得後退学。博士(文学)(2003年、東京都立大学)。マサチューセッツ工科大学言語学・哲学科、エジンバラ大学言語進化・計算研究ユニットにてVisiting Scholarとして研究に従事。愛知県立大学、上越教育大学を経て、津田塾大学学長補佐(学務担当)・学芸学部英文学科教授。日本英語学会理事、評議員、編集委員、大会準備委員会委員長、市河賞選考委員、東京言語研究所理論言語学講座講師等を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
bapaksejahtera
寛理
ニッポニテスは中州へ泳ぐ
御光堂
-

- 和書
- 恐竜・古生物No.1図鑑