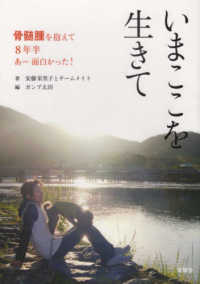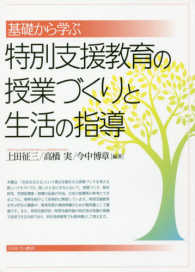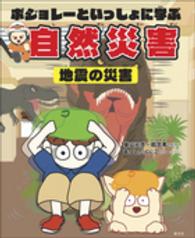出版社内容情報
創造の源を探るべく、作者が身を置いていた時代に立ちもどり、資料を博捜し、緻密な考証に基づき五彩豊かな鏡花世界の再現を試みる。明治大正昭和の三代にわたる旺盛な創作活動を展開した泉鏡花。その豊穣な世界は、作者を取り巻く現実とのきびしい対峙によってはじめて創出されたとの認識から、生涯の全体を俯瞰した総説に続き、日清戦後の観念小説の分析を行い、二度に及ぶ逗子滞在期の「逗子もの」の位相を定め、すすんで大正期を特徴づける長篇小説読解の基礎を固めて、さらに能楽や近世文芸からの深い影響を本格的に実証。鏡花作品の上演史についても、従来の理解を一新する、より総合的な把握を提示した。本書の論考は、厳密な年譜考証に基づき、作者の伝記的事実を確定、素材典拠を博捜して発想の源を探るとともに、自筆原稿の調査をふまえ、作品生成の過程をつぶさにたどったところに特徴がある。
[凡例]
泉鏡花素描
?
1 ふたつの「予備兵」―泉鏡花と小栗風葉―
2 観念小説期の泉鏡花―兵役と戸主相続の問題を通して―
3 「海城発電」 成立考
4 泉鏡花と広津柳浪―「化銀杏」と『親の因果』の関係―
?
1 「通夜物語」のかたち
2 逗子滞在と「起誓文」「舞の袖」
3 祖母の死と「女客」
4 「瓔珞品」 素材
5 「草迷宮」 覚書―成立の背景について―
6 「歌行燈」 覚書―宗山のことなど―
?
1 「印度更紗」 と漂流記「天竺物語」
2 「芍薬の歌」 ノート
3 「由縁の女」 の成立をめぐって
4 「露宿」 をめぐって―鏡花の随筆―
?
1 鏡花のなかの一葉―「薄紅梅」を中心として―
2 泉鏡花と草双紙―「釈迦八相倭文庫」を中心として―
3 鏡花の転居
4 泉鏡花と演劇―新派・新劇との関係から「夜叉ケ池」に及ぶ―
[後記]
[索引] 泉鏡花著作索引、人名・書名・事項索引
吉田昌志[ヨシダ マサシ]
昭和30年3月 長野県諏訪市生れ。
昭和53年 青山学院大学文学部卒業。昭和59年 青山学院大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。昭和61年より昭和女子大学に勤務、現在同大学大学院教授。
『泉鏡花“美と永遠”の探究者』(日本放送出版協会)のほか「新日本古典文学大系明治編」14『泉鏡花集』、『新編泉鏡花集』、『鏡花随筆集』(以上岩波書店)等の編著がある
内容説明
緻密な考証に基づく描線によって、五彩豊かな鏡花世界を再現。幻想、怪奇、妖美のみでは語りつくせぬ、多様にして重層的な泉鏡花の文学。その創造の源を探るべく、作者が身を置いていた時代に立ちもどる。厳密な年譜考証に基づき、作者の伝記的事実を確定、素材典拠を博捜して発想の原点を求めるとともに、自筆原稿の調査をふまえ、作品生成の過程をつぶさにたどる。
目次
1(ふたつの「予備兵」―泉鏡花と小栗風葉;観念小説期の泉鏡花―兵役と戸主相続の問題を通して;「海城発電」成立考;泉鏡花と広津柳浪―「化銀杏」と『親の因果』の関係)
2(「通夜物語」のかたち;逗子滞在と「起誓文」「舞の袖」;祖母の死と「女客」;「瓔珞品」の素材;「草迷宮」覚書―成立の背景について;「歌行燈」覚書―宗山のことなど)
3(「印度更紗」と漂流記「天竺物語」;「芍薬の歌」ノート;「由縁の女」の成立をめぐって;「露宿」をめぐって―鏡花の随筆)
4(鏡花のなかの一葉―「薄紅梅」を中心として;泉鏡花と草双紙―「釈迦八相倭文庫」を中心として;鏡花の転居;泉鏡花と演劇―新派・新劇との関係から「夜叉ケ池」に及ぶ)
著者等紹介
吉田昌志[ヨシダマサシ]
昭和30年3月長野県諏訪市生まれ。昭和53年青山学院大学文学部卒業。昭和59年青山学院大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。昭和61年より昭和女子大学に勤務、現在同大学大学院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
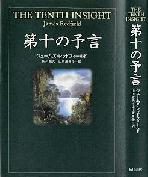
- 和書
- 第十の予言