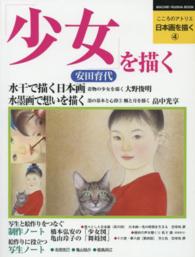内容説明
人魚とはいかなる生物なのか、人々は長い人類の歴史の中でこれらの人魚の描写を通して何を伝えようとしたのか。人間と魚とが合体したといわれる半人半魚の想像上の動物「人魚」は古今東西を問わず様々な文献に登場する。井原西鶴の『武道伝来記』等の文学作品を初め、大槻玄澤の『六物新志』等の博物学や民俗学の文献も取り上げ、日本以外の地域の文献、例えば古代中国の地理書『山海経』やアンデルセンの童話「人魚姫」等も加え、「人魚」の実像に迫る。
目次
江戸時代の「人魚」像(1)―文学作品に登場した「人魚」
江戸時代の「人魚」像(2)―博物学の舶来を中心として
江戸時代以前の「人魚」像―日本における「人魚」像の原点へのアプローチ
明治時代の「人魚」像―西洋文化の流入と「人魚」への影響について
大正時代の「人魚」像(1)―翻訳文学と「人魚」
大正時代の「人魚」像(2)―アンデルセンの童話「人魚姫」の受容
昭和時代の「人魚」像(1)―翻案小説の「人魚」像
昭和時代の「人魚」像(2)―戦争体験と「人魚」像
日本の「人魚」伝説―「八百比丘尼伝説」を中心として
「人魚」の実像考―民間伝承の中の「怪物」の正体について
ギリシア・ローマ時代の「人魚」像―ヨーロッパの「人魚」像の原点、「セイレーン」を中心として
一八世紀以前のヨーロッパの「人魚」像―「セイレーン」から「マーメイド」へ
著者等紹介
九頭見和夫[クズミカズオ]
福島大学名誉教授、「福島県文学賞」審査委員(小説部門)。東北大学大学院文学研究科(独語・独文学専攻)修了。日本独文学会理事、日本比較文学会東北支部長、東北大学・高知大学・放送大学等非常勤講師を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りりす
メルセ・ひすい
サチ
トト
fuchsia