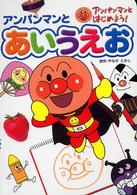内容説明
あの頃、ソンタグがいた―真摯であること、注意を傾けること、真実を語ること。しなやかな感性とクリティカルな知性、スーザン・ソンタグのラスト・メッセージ。
目次
美についての議論
一九二六年―パステルナーク、ツヴェターエヴァ、リルケ
ドストエフスキーの愛し方
二重の宿命―アンナ・バンティ『アルテミジア』について
消し尽くされぬもの―ヴィクトル・セルジュをめぐって
異郷―ハルドール・ラクスネス『極北の秘教』について
9.11.01
数週間後
一年後
写真―小研究〔ほか〕
著者等紹介
ソンタグ,スーザン[ソンタグ,スーザン][Sontag,Susan]
1933年生まれ。批評家・作家。米国で最も精力的な知的営為を続けた批評家のひとり。2004年歿
木幡和枝[コバタカズエ]
上智大学卒。アート・プロデューサー。東京芸術大学先端芸術表現科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
踊る猫
39
遅まきながらソンタグのエッセイを読んだのだけれど、予期していた理知的で高飛車な人というイメージを裏切る実にホットなエッセイ/批評が並んでいると思った。大量に情報を詰め込むことで対象を微細に分析し、浮かんだアイデアをつぶさに書き留めて煩雑になることを恐れない。そして、そのアイデアの羅列はいまに至るもその強度を失っていないことにも戦慄さえ感じる。ここまで見渡せていたのはソンタグがアメリカの中だけで閉じられていた視野の持ち主だったからではなく、世界を見渡して高いところから語れる人だったからだ。この見識、侮れない2023/12/02
三柴ゆよし
28
死の床にあっても、自分はまだ生きて書く、という意志を失わなかったソンタグの最晩年のエッセイ、講演をまとめたもの。911着後という最もセンシティブな時期にアメリカの指導層のあり方を激烈に批判した有名なコメントも収録されているが、個人的に白眉と思ったのは「美についての議論」。短文ながら、審美論の変遷をたどりつつ、現代人が広く芸術全般に向き合う姿勢について問い直す、背筋の伸びるようなエッセイ。自分の感性と知性によほどの信頼がなければソンタグのような文章はとても書けないが、どうしたってあこがれる作家のひとりだ。2019/10/25
とみぃ
17
twitter=さえずり、chat=おしゃべり、が盛んである。誰もが、私もまた、こうした場でおしゃべりを楽しんで、つかの間の愉快に浸る。ソンタグさんは、言葉や美の観念などの個人化・相対化が進行していることに警鐘をならす。消費時代には、「美しい」よりも「面白い」が優位化され、それが衝突を好む心情を背景としているという指摘は、さすがの炯眼と思った。また、拷問の前でポーズを取って写真を撮ることについて、楽しみ(fun)のためなら他人のことはどうでも良いという心性があるという指摘も、痛いところをつくなあと思った。2020/05/30
chanvesa
17
「美についての議論」の「面白い」という価値基準の指摘は興味深い。現代美術の展覧会では、ポレミックな内容の作品が多いと思うからだ。ではそれが美かどうか、そもそも美って何かを考えていったらよくわからない。「あの夕日、面白くない?」は「あり」ではないか?夕日のような日常的な存在が、面白いと思わせる何か異質なものがあって、それがなんだかわからないけど、美である可能性は存在する気がする。「数週間後」の9.11と真珠湾の違い(敵が一国か複数か)は、この時には結果論的な指摘だったが、イスラム国の出現で、説得力を増した。2014/10/13
メタボン
11
☆☆☆ 知の巨人という印象。著作に対しては何度も推敲を重ねるということだが、「言葉」に対する「信仰」のようなものがあるのかもしれない。「旧いものがなくては困る。私たちのすべての過去、叡智、記憶、悲しみ、現実感覚が投入されているから。新しいものに対する信念がなくても困る。私たちのすべてのエネルギー、楽観主義に向かう能力、無意識の生物学的な欲求、忘却の能力-あらゆる和解に欠かせない治癒能力-が投入されているから。」他には、ロシアの埋もれた作家たちに対するリスペクトが印象に残った。2014/08/24
-
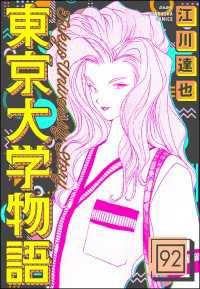
- 電子書籍
- 東京大学物語(分冊版) 【第92話】 …
-

- DVD
- 日本怪談劇場 第4巻