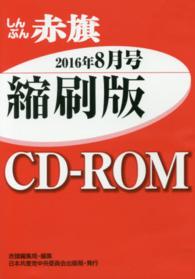内容説明
最高の評価を得たレストラン『ゼフィーロ』の成功の裏には、意外なストーリーが隠されていた―著名な評論家である父の特異な教育方針のもと、食への飽くなき探求を続けた著者が、ナディア・サンティーニら料理の天才たちとの交流、欧州を縦断する修業の旅を経てたどりついた「味の神髄」とは。
目次
第1章 なぜあなたの料理店選びはまちがっているのか(料理店に必要なものは、お客様・食材・お金;料理店の良し悪しは客層に表れる ほか)
第2章 いい料理人はどうすれば育つのか(人と同じでは多くの中に埋まるだけ;私流の経営原則 ほか)
第3章 わたしはこのように「食」の世界に引きずり込まれた(外国で暮らした幼少時代、父の後ろ姿;海外生活で見たものと帰国後のいじめ ほか)
第4章 料理界のルネッサンスのために―わたしの訴え(料理人と生産者との密な関係が日本文化の危機を救う;我々にできるサポートとは? ほか)
著者等紹介
西部一明[ニシベカズアキ]
1969年、西部邁(秀明大学学頭・評論家)の長男として東京に生まれる。辻調理師専門学校フランス校にて秘書兼通訳として勤務後、イタリアの三ツ星レストラン『ダル・ペスカトーレ』等で修業。2002年、レストラン『ゼフィーロ』設立。現職は早稲田大学公共政策研究所客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroki Nishizumi
2
題名からして食べ歩きの本だと思ったのに全く違ってました。著者である西部一明氏のこれまでの生涯と思い、という題の方がよろしいかと思います。それでもインテリの御曹司だけあって学者的な分析が興味深く楽しめました。料理店の良し悪しは客層に表れる、リーズナブルとは総合的に納得できること、大量生産こそ危機の根本、サラリーマンになるなかれ、料理店はオーケストラということ・・・等々普遍的原理原則が学べます。業際的事業方向性の展開の参考になりました。2013/08/04
boya
1
日本における理想の食文化と料理人の心構えを追求した「坊ちゃん」物語。自身の特異な経歴に基づく記述がほとんどで、取材をしていないため、題名のような期待をしても役には立たない。しかし、ところどころに華を添えている独特のエピソードには、他業種であっても首肯できる普遍性がある。2012/10/04
YOS1968
1
著述家の西部邁氏の長男である一明氏が開いた西麻布のゼフィーロというレストランの話である。ワインや料理云々でなく、店の経営というごくまっとうな問題に対して真摯に考えている氏の姿勢は一流だと思った。2010/01/17
Naota_t
0
題名が扇情的で手にとりましたが、内容の満足度は微妙でした。 正直、「さいですか…がんばったんやね」というくらいの感想でした。 フランスで料理経験があり、日本に帰ってフランス料理店(5年で閉店)を経験した著者が語る、「料理店とは何たるか」論みたいな感じです。 「本当においしい料理店に出会える」方法を説いた本ではないです。 著者の愚痴というか、経験談を語って、結局は日本じゃ出会えない、もしくは超難しい、どこの店もある程度繕っています、という結論です。 2013/04/30