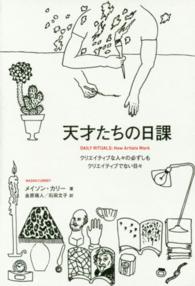内容説明
作家が生きた言説の歴史的現場に身を置き、さまざまな関係性のなかで流動化する作家と作品を緻密に検証する。初期作品、そして「或る女のグリンプス」から『或る女』への改稿過程を辿り、可能性としての「作家」を発見する、有島文学研究の気鋭による文学神話解体の試み。
目次
序章 「作家」の生成、あるいは解体
1 有島武郎の生成(初期言説にみる歴史意識の変容;『かんかん虫』の位相;「或る女のグリンプス」の変質)
2 「作家」としての有島武郎(有島武郎という記号;『平凡人の手紙』の波紋―大正期文芸批評論の展開;『カインの末裔』の方法)
3 『或る女』をめぐって(『或る女』前編の改稿;『或る女』の方法;『或る女』の劇と空間)
4 書くことの行方(書くことの疎外と統一―『生れ出る悩み』の可能性;『星座』の孤独/書くことの孤独―有島武郎「晩年」への一視角)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
澄川石狩掾
1
再読。 「書く」ということを主な観点として有島武郎のテクストを論じており、筆者によれば、「書く」ことは基本的には孤独であるが、「生れ出づる悩み」では君―私―読者と接続する可能性がある一方、『星座』にも現れる「書く」という行為は各登場人物の孤独を深めるという。 また、筆者は『或る女』や『星座』を論じる際、「語り手」を中心に置いているが、「語り手」というものを絶対視しすぎている嫌いがある。 内容には直接関係ないが、「~するだろう」、「~したであろう」という表現が頻出したのが、気になった。2020/05/08