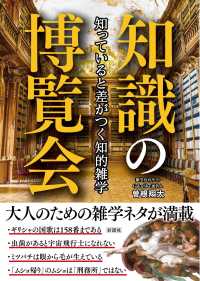目次
第1部 製パン原材料(小麦粉;パン酵母(イースト)
製パン改良剤(イーストフード) ほか)
第2部 製パン工程(原材料の選択;原材料の計量;ミキシング(混捏) ほか)
第3部 製パンの基本と応用(基本のパン;プロ必須のアイテムとその製法;店の技術力が示せるドイツパン)
著者等紹介
竹谷光司[タケヤコウジ]
1948年北海道生まれ。北海道大学を卒業後、山崎製パン入社。ハリー・フロインドリーブ氏の紹介で3年間旧西ドイツ(現ドイツ)でパンの研修を受ける。1974年に帰国と同時に日清製粉に入社。日本製パン技術研究所(JIB)、アメリカ製パン技術研究所(AIB)を経て1986年、日本の若手リテイルベーカリー有志とベーカリーフォーラムを立ち上げ、今日のベーカリー発展の礎を築く。その後ミックス粉、小麦、小麦粉、製粉、食品の基礎研究に携わり2007年、製粉協会・製粉研究所へ出向、全国の育種家の知己を得る。2010年、千葉県佐倉市に「美味しいパンの研究工房・つむぎ」開店(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
8
図書館にて。いわゆる町のパン屋(Not山崎パン)向けの本である▲以前は小麦と水をよく混ぜることによってグルテンが作られてゆくと考えられてきた。現在では、水をかけたらすぐグルテンの玉(ダマ)ができ、それを練って延ばしてシート上にしてゆくと分析された▲「天然酵母」アピールのせいでイーストが化学合成みたいなイメージが広がったため、いまではパン酵母と呼んでいる。もちろん、ブツは同じ▲生地や形成した段階で冷蔵・冷凍する製法。1週間くらい保つのでまとめて作れる。砂糖は発酵を阻害するが、逆にいうと冷蔵耐性が増す。2021/03/21




![一等兵戦死 - 普及版[復刻版]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48024/4802401477.jpg)