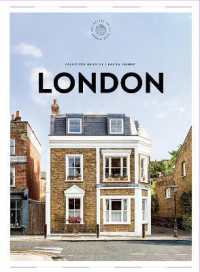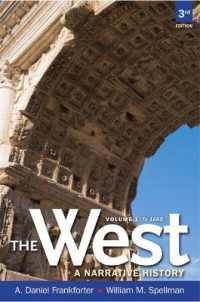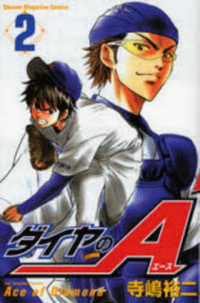内容説明
20世紀美術を動かした真の芸術家たちは誰か―。近代芸術はいかに展開したか、その根幹から把握する、美術史的傑作。
目次
第1部 抽象の力 本論(抽象の力;キュビスムと「見えないもの」 ほか)
第2部 抽象の力 補論(守一について、いま語れることのすべて;先行するF ほか)
第3部 メタボリズム―自然弁証法(名を葬る場所;白井晟一という問題群 ほか)
第4部 具体の批評(批評を招喚する)
著者等紹介
岡崎乾二郎[オカザキケンジロウ]
1955年東京生まれ。造形作家、批評家。絵画、彫刻、映像、建築など、ジャンルを超えて作品を創造するとともに、美術批評を中心に執筆を続けてきた。1982年のパリ・ビエンナーレに招聘されて以来、数多くの国際展に出品し、2002年にはセゾン現代美術館にて大規模な個展を開催。また、同年に開催された「ヴェネツィア・ビエンナーレ第8回建築展」の日本館にディレクターとして参加するなど幅広い活動を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
17
抽象芸術の閉じられた可能性を、近代日本美術と西洋美術との共時性に基づきながら、さらには夏目漱石をはじめとする文学的思想と併走させながら、再度開いていく。そうした野心を、強い筆致で描いていく言葉が見事。最後の、1962年に焦点を置いた批評に関する小論で綺麗なオチまでついている。ゾフィー・アルプなど、女性作家への言及が多いのも気になるポイント。図書館の本だけど、改めて買った方が良さそう。2019/10/23
Bartleby
13
「抽象の力」と題されているが中身はきわめて具体的。議論の前提となる知識すら自分には欠けていることを実感。超俗の仙人的イメージのある熊谷守一像が、180度変わった。抽象表現という文脈においていかに理論的・方法的だったかが本書を読むとわかる(同時代人たちにとっては周知の事実だったそうだけど)。岡崎乾二郎の本はつねに具体的で、雑な思考を決して許さない。論じている対象がありありと目の前にあるようなモノ感があり、外部世界と常時接続していて風通しがよい。2023/04/10
しゅん
12
本論のみ再読。人間の感覚をより微細に捉えようとする科学・哲学・精神分析が広がりゆく20世紀前半にかけて、美術と文学がどのように感覚的な作品(抽象作品)を作っていったかの歴史。描写対象の明確な写実性や「地と図」の二元論が解体され、キュビズム・ダダイズム・新感覚派などの芸術・文学運動が生まれゆく。戦争との関わりをかわしながら、教育と日常生活への応用を模索する。そうした抽象の歴史において、ゾフィー・トイベル=アルプやカルメン・ヘレラなどの女性の業績を再評価していく。2025/08/29
eirianda
10
あとがきから、『そもそも制作者は結果物の差異そのものよりも、いかにこれがつくられたのか、その差異を生み出した制作過程そして「設計思想」そのものに興味を持つ。一方、美術史は影響関係を調査しようとするとき、その裏付けを実際の人的交流や作家の具体的な言及などの資料に求めようとする。』まさにまさに。時代背景が変わっても惹きつける作品とはどういうものか。それともこういった批評込みで選ばれし作品は後世まで残るのか。抽象も要は言葉か。fとFは内的視点と俯瞰かな。創作にはとても大事。2020/05/31
MO
6
抽象絵画について調べたらヒルマ・アフ・クリントに辿り着いた。抽象画の起源を知りたかったので、彼女の名前をググったら日本語でこの本しか出てこなかった。読んでみたけどヒルマの言及はほんの数ページ、とほほ。抽象画については半分で後は抽象芸術の概念が作品に影響、作用しているかを作家ごとに解析している。著者のリサーチの深さや、洞察、見識、思いの熱さにページが進むが読み手に広い知識が求められる。しかも話が期待したものでなくて、途中から自分は何を読んでいるんだと迷子になった。著者は美大の先生で自信も抽象画家でした。2021/07/29
-

- 電子書籍
- DIME (ダイム) 2020年 1月号