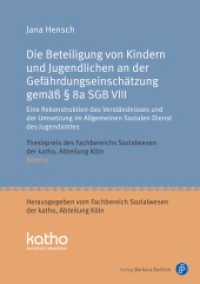目次
はじめに―「ろう文化」への招待
第1章 ろうであることの発見
第2章 ろうのイメージ
第3章 異なる中心
第4章 聴者の世界で生きる
第5章 手話への新しい理解
第6章 音のもつ意味
第7章 歴史的創造物としてのろうの生活文化
著者等紹介
パッデン,キャロル[パッデン,キャロル] [Padden,Carol]
1955年、ろう家族のもとにろうとして生まれる。ジョージタウン大学卒業。カリフォルニア大学サン・ディエゴ校で手話言語学の分野で博士号を取得。現在、同校教授
ハンフリーズ,トム[ハンフリーズ,トム] [Humphries,Tom]
1946年生まれ。ギャローデット大学卒業。ユニオン大学院で比較文化と言語習得の分野で博士号を取得。現在、カリフォルニア大学サン・ディエゴ校のコミュニケーション学部で専任講師を務める
森壮也[モリソウヤ]
1962年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部経済学科、同大学院経済学研究科修了を経て、日本貿易振興機構アジア経済研究所開発研究センター主任調査研究員。横浜国立大学、横浜市立大学、日本福祉大学、日本社会事業大学などで非常勤講師。日本手話学会元会長、『手話学研究』編集委員会委員長、Sign Language Studies前Editor。障害学会元理事
森亜美[モリアミ]
1962年、東京都生まれ。早稲田大学第一文学部史学科西洋史学専修卒業。東京銀行(現三菱東京UFJ銀行)本店調査部勤務などを経て、デフ・マザーズ・クラブを設立(2003年解散)。東京都聴力障害者情報文化センター英語教室講師、日本社会事業大学、筑波技術大学で非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ドシル
みっふぃー
水紗枝荒葉
石