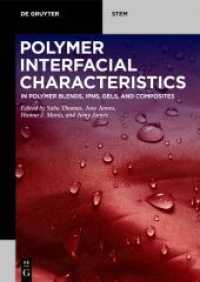出版社内容情報
●内容紹介(版元ドットコムより)
アメリカをはじめ日本と韓国・旧ソ連諸国・カリブ海諸国など死刑維持国と廃止国の国際的動向を踏まえ死刑制度を多角的・批判的に検討し問題点を抽出する。廃止と代替制度に関する提言は、日本の裁判員制度や被害者の裁判参加の問題へ重要な示唆を与える。
●目次(版元ドットコムより)
序
1章 死刑――改善か、それとも廃止か
2章 国際法と死刑――変化の反映か促進か
3章 医師と死刑――倫理と残虐な刑罰
4章 死刑の代替――代替的制裁という結論の出にくい争点
5章 アメリカ合衆国における宗教と死刑――過去および現在
6章 乱雑な死刑執行について
7章 シャリーアにおける刑罰としての死
8章 アメリカ合衆国における死刑廃止――制度の障害および将来の可能性の分析
9章 アメリカ合衆国における死刑――執行停止への努力と主な動向
10章 リトアニアの死刑廃止への実験
11章 韓国と日本の死刑――「アジアの価値」そして死刑に関する論争
12章 旧ソビエト連邦共和国グルジアにおける死刑廃止戦略
13章 カリブ海諸国における死刑――植民地の遺産、植民地の権利の実現方法
14章 世論と死刑
15章 死刑――殺人の被害者および死刑囚の家族の要求に応えること
注
監訳者あとがき
●本書より(版元ドットコムより)
監訳者あとがき
本書Capital Punishment - Strategies for Abolition(2004)(邦訳『死刑制度――廃止のための取り組み』)が編者の一人であるホジキンソン氏から出版直後に送られてきた。魅力ある書名を見て、どうしても邦訳する必要があると思い、明治大学大学院の院生を中心に翻訳に着手した。それ以来、すでに5年有余がすぎた。予想外の遅延は、むろん監訳者に主たる要因があるが、本書(15章)の1章ごとに15人が手分けして翻訳したためその訳語の統一に手間取った。
編者の一人であるホジキンソン氏とは旧知の間柄であるが(彼の略歴については別項参照)、2005年12月に彼が来日した際、イギリス大使館の招待で日本の死刑問題について語るため昼食をともにする機会があった。そのときは翻訳書を1年後には出版予定だと話したが、その約束は果たせなかった。彼からは、いつごろ出版されるかとの問い合わせが再三寄せられていたが、ようやくここに約束を果たすことができた。
本書が、日本における死刑廃止運動にとって貴重な示唆を与えるものであることは読者がおのずから理解されるものと確信する。ここでは、あえて日本における死刑廃止への現状を国際的な視野をも考慮するなかで検討し、本書の位置づけを述べておきたい。
最初に指摘したいことは、オバマ氏がアメリカ大統領に就任したことと死刑制度との関連である。彼自身は現時点では、アメリカの死刑については語っていないように思われるし、「合衆国」としてのアメリカ大統領が死刑廃止へのイニシアチブをどれだけ取れるかの制度上の問題はある(州の死刑制度は連邦政府の管轄外である)。それでも人種差別への徹底的挑戦を標榜するオバマ政権が死刑廃止に消極的であるはずがない、と私は考えている。何よりも死刑問題はアメリカ国内の問題だけではなくて、今や国際的動向のなかで必然的に動かされる状況にあるからである。
オバマ氏がアメリカ大統領に就任したこと自体がアメリカそのものが人類的規模で動いていることを感じるからでもある。その大統領就任の時期において、100年に一度といわれる経済恐慌を世界が体験している。その背景にはアメリカのサブプライムローンの失態が原因とされているものの、これまでの経済・金融政策では対処できない課題として問題が浮上している。ここで求められているのは、国境を越えた、より強力な経済・金融の組織作りであり、この課題はアメリカが直面しているテロ対策にも求められている。ニューヨークでの9.11事件のテロ実行犯とされる容疑者は世界に散らばっていると言われているが、その容疑者を死刑を存置しているアメリカへ引き渡すことを死刑廃止国は拒否している。死刑の存否はその国の国内問題であるとしている時代ではなくなっている。経済・金融そして刑罰のあり方(死刑のあり方)が単なる国家単位の問題ではない時代にある。
アムネスティ・インターナショナルの調査では現在、世界のほぼ200か国のうち事実上の廃止国を含めて138か国が死刑を廃止または10年以上の執行停止をしている。世界の過半数は優に超えている。なかでもEU加盟国は26か国がすべて死刑を廃止し、フランスは憲法に死刑廃止条項を書き加えた。それは世界にその国の価値観を示すためであるとされている。そのヨーロッパの価値観からすれば、野蛮な絞首刑を今も実施しているダーティーな日本国、その日本の近代産物である自動車や工業製品を買うことを拒否すべきであるとの運動がヨーロッパで叫ばれている。
ところが国連人権委員会の再三にわたる日本への死刑執行停止(モラトリアム実現)の勧告に逆行し、いまや日本は世界有数の大量死刑執行国である。それが現政権の価値観のありようにあることは言うまでもないが、一方において死刑廃止グループが死刑の執行あるごとに単に抗議集会を繰り返すだけで足りるとはだれも思ってはいないはずである。時の死刑存置権力に抗議する死刑廃止運動も盛んではある。しかし運動そのものが果たして日本の死刑廃止への確実な前進に寄与してきたかと言えば、運動が盛んになるのに逆行して死刑存置の世論と執行数を増大させてきた不幸な現状を直視しなくてはならない。
死刑廃止への運動に即効薬はない。死刑廃止に向けて可能なことを淡々とやるしかないというのが私の持論ではあるが、死刑制度の問題は、単に国内問題としてだけではなく国際的人権問題であり、それは世界の金融、経済政策にも共通する人類的課題でもあることを改めて認識しなくてはならない。本書は、このような視点から死刑廃止への戦略を展開している。その具体的提言は本書にゆだねるが、本書の編者の一人であるホジキンソン氏は「死刑に関する国際基準」を提示し、死刑に代替する論議の必要性を強調している。その注目すべき提言の一つは、死刑廃止グループで議論する暇があれば死刑存置者との議論に、より多くの時間を費やすべきである、ということであり、他の一つは、死刑廃止への「架け橋」として仮釈放のない終身刑を新設することである。
本書が死刑廃止運動の一助となれば幸いである。
2009年3月15日
菊田 幸一
目次
死刑―改善か、それとも廃止か
国際法と死刑―変化の反映か促進か
医師と死刑―倫理と残虐な刑罰
死刑の代替―代替的制裁という結論の出にくい争点
アメリカ合衆国における宗教と死刑―過去および現在
乱雑な死刑執行について
シャリーアにおける刑罰としての死
アメリカ合衆国における死刑廃止―制度の障害および将来の可能性の分析
アメリカ合衆国における死刑―執行停止への努力と主な動向
リトアニアの死刑廃止への実験
韓国と日本の死刑―「アジアの価値」そして死刑に関する論争
旧ソビエト連邦共和国グルジアにおける死刑廃止戦略
カリブ海諸国における死刑―植民地の遺産、植民地の権利の実現方法
世論と死刑
死刑―殺人の被害者および死刑囚の家族の要求に応えること
著者等紹介
ホジキンソン,ピーター[ホジキンソン,ピーター][Hodgkinson,Peter]
ロンドン・ウェストミンスター大学ロースクールの死刑研究センター(Centre for Capital Punishment Studies)の創設者で所長。1989年にウェストミンスター大学に加わる以前は、インナーロンドン保護観察庁(Inner London Probation Service)の保護監察官を15年間務めた。その間に、終身刑を宣告され精神的に不調を来した犯罪者の管理への関心と専門的知識を高めた。欧州評議会の死刑に関してのアドバイザー、そして英国外務大臣の死刑委員会(Death Penalty Panel)の一員として数多くの国の政府当局と協力してきた。そして、死刑の代替に関しての議論を展開している。死刑に関する著作多数。2005年12月に東京で開かれた「人権と死刑を考える国際リーダーシップ会議」に参加し死刑をめぐる国際情勢や死刑に関する国際基準について発言をしている
シャバス,ウィリアム・A.[シャバス,ウィリアムA.][Schabas,William A.]
国立アイルランド大学人権法教授、アイルランド人権センター所長。専門は国際人権法および刑法。トロント大学文学修士、モントリオール大学法学博士
菊田幸一[キクタコウイチ]
1934年生まれ。明治大学名誉教授・法学博士。現在、弁護士・明治大学犯罪学研究所長。中央大学法学部卒業(1957年)後に、明治大学大学院で犯罪学を専攻、博士課程在学中に法務省法務総合研究所研究官補(1962年)となり、カリフォルニア大学犯罪学部に留学(1963~1964年)、明治大学法学部専任講師(1967年)、同教授(1975年)を経て、2005年同大学退職。2004年より、弁護士として主に刑事弁護に当たっている。2001年6月の第1回死刑廃止国際会議団長、法務省行刑改革会議委員などを歴任し、現在NPO法人「全国犯罪非行協議会」理事長、「監獄人権センター」副会長。日本における死刑廃止運動リーダーの一人。最近は死刑の代替として終身刑の導入を主張している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 新大学原論