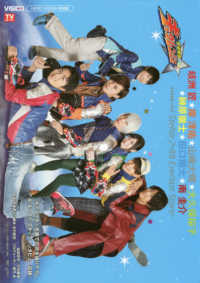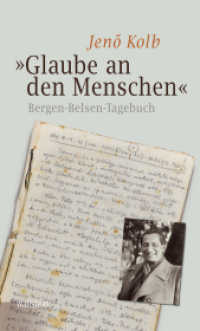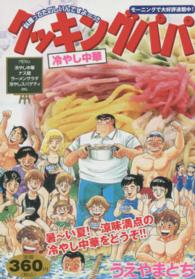出版社内容情報
98年に秋野豊氏が紛争解決の活動中に銃弾に倒れてから10年。この間もユーラシアの各地では紛争は絶えない。秋野賞受賞者など新進気鋭の専門家が、紛争現場と研究の最前線を紹介。紛争解決や平和構築に関心を持った人々のよき入り口となる一書。
はじめに――あなたが本書を手にする7つの理由
第1部 東アジア
第1章 東アジア地域の概観(小笠原高雪)
第2章 中国(佐々木智弘)
第3章 朝鮮半島(道下徳成)
第4章 カンボジア(山田裕史)
第5章 東ティモール(安藤友香、清水麻衣子)
第2部 ロシア・中央ユーラシア
第1章 ロシア・中央ユーラシア地域の概観(湯浅剛)
第2章 ロシア(湯浅剛)
第3章 グルジア(小山淑子)
第4章 中央アジア(稲垣文昭、中西健)
第3部 中東・南西アジア
第1章 中東・南西アジア地域の概観(江崎智絵)
第2章 イスラエルとパレスチナ(江崎智絵)
第3章 イラク(岸田圭司)
第4章 アフガニスタン(上杉勇司、瀬谷ルミ子)
第4部 欧州
第1章 欧州地域の概観(広瀬佳一)
第2章 ボスニア(吉留公太)
第3章 コソボ(久保慶一)
第4章 モルドバ(南野大介、末澤恵美)
第5部 国際紛争への日本の取り組み
第1章 政府の役割(河東哲夫)
第2章 NGOの役割(金敬黙)
第3章 日本のアプローチ(上杉勇司)
あとがき
略語表
索引
編著者、執筆者紹介
はじめに――あなたが本書を手にする7つの理由
1 ラスト・サムライ
秋野豊は10年前にタジキスタンで凶弾に倒れた。国連政務官としてタジキスタンの和平プロセスを支援するために紛争当事者の間を奔走しているときだった。秋野はユーラシア大陸のど真ん中で紛争解決の処方箋を書くことを目指していたという。本書はラスト・サムライと呼ばれた秋野の遺志を継ぐ者たちによって執筆されている。だから、問題の指摘にとどまらず、あえて平和のシナリオを提示することに挑戦した。
2 ユーラシアと日本の接点
本書で扱うユーラシア地域とは、西は欧州から東は北東アジアまでである。本書の各章で解説していくように、ボスニア、コソボ、パレスチナ、イラク、アフガニスタン、北朝鮮など、多くの火種を抱えるユーラシア地域の紛争解決と平和構築は、私たち日本人にとっても、そして世界の人々にとっても切実な課題である。まさに、ユーラシア地域の平和が、世界や日本の平和の要となるといっても過言ではない。
3 紛争解決の処方箋
だが、率直に言って、本書で紹介されるユーラシア地域の紛争と平和の現状と課題を理解すればするほど、平和のシナリオを描くことは容易ではなかった。前途多難な平和構築の道のりに存在する課題を指摘することはできても、紛争に苛まれた社会を平和な社会へと確実に導く「紛争解決の処方箋」を書くことは予想以上に難しかった。これには、紛争の複雑さも影響しているが、それ以上に従来の私たちの紛争解決や平和構築に対する姿勢に問題があるのではないかと考えるようになった。
4 複眼的な平和のシナリオ
例えば、これまでの平和研究は、紛争の要因であったり、平和を妨げたり脅かしたりする要因を分析することに多くの時間を割いてきたが、特定の社会において紛争が平和裡に解決され、人々が平和を享受している理由を解明する努力が足りなかった。つまり、平和研究の実態は紛争研究であり、平和を研究してこなかったといえる。平和構築の研究においても、平和構築の複雑さや難しさを指摘するものは多いが、成功の要件について実証研究を行ったものは少ない。平和構築の文脈において、平和が持続可能なものになるためには、現地社会の政治・社会的な特性や歴史・文化的な背景を考慮し、現地社会が主体的に平和構築を担っていく必要があることが指摘されて久しい。だが、それではどのようにこれらを実現していけばよいのか。本書を取りまとめる過程で私たちがたどり着いた結論は、地域研究、平和・紛争研究、平和構築の実務などを織り交ぜた複眼的な視点から平和のシナリオを思い描かない限り、紛争解決の処方箋を書くことはできないということだ。
5 戦略思考の必要性
さらに、実務家の視点からは、特定の地域、特定の条件下、例えば現在のアフガニスタンにおいては、どのように平和構築を進めていくのがよいのか、といった問いへの答えが必要である。アフガニスタンの政治・社会的な特性や歴史・文化的な背景を考慮したときに、実現可能な平和へのシナリオは、例えばカンボジアや東ティモールの平和構築と比べた場合に、どこがどのように違うのか。平和構築のゴールが明確に見いだせないかぎり、そこに向かうシナリオは描けない。長期的なビジョンがなければ戦略を立てることはできない。その場その場で直面する課題をひとつひとつ解決していくことは、短期的には平和構築の成果としてとらえることができても、それが持続可能な平和に結びつく保証はないからだ。
6 熱き心と冷徹な頭脳
このような問題意識に突き動かされて書かれている本書は、各地域の歴史や社会的背景をふまえつつ、紛争解決と平和構築の現場と研究の最前線における試行錯誤を紹介し、矛盾や苦悩の中から生まれる光を探している。事象を客観的に分析・記述してゆく冷徹な目線のみならず、人の心を揺さぶるくらいの情熱とコミットメントに従って本書は書き進められた。
7 秋野豊の磁力
私たち執筆者が本書に込めた思いは3つある。まずは、本書を紛争解決や平和構築に関心を持った人々にとっての、よき入り口とすること。次に、私たち自身が大いに関心を持ち、今後の紛争解決・平和構築に重要であると考える論点を整理し、読者に提示すること。最後に、本書を私たちが大事にしている「紛争と平和」、「研究と現場」、「協働と自立」の3つの対立軸が重なり合う空間としてとらえ、そこから創造的な磁力を生み出すこと。本書によって、情報過多の時代にどのような基準にもとづいて関心を追求していけば、「紛争解決の処方箋」を書くことができるようになるのかを示したつもりである。秋野豊の磁力によって集められた英知は本書に結集した。
目次
第1部 東アジア(東アジア地域の概観;中国;朝鮮半島;カンボジア;東ティモール)
第2部 ロシア・中央ユーラシア(ロシア・中央ユーラシア地域の概観;ロシア;グルジア;中央アジア)
第3部 中東・南西アジア(中東・南西アジア地域の概観;イスラエルとパレスチナ;イラク;アフガニスタン)第4部 欧州(欧州地域の概観;ボスニア;コソボ;モルドバ)
第5部 国際紛争への日本の取り組み(政府の役割;NGOの役割;日本のアプローチ)
著者等紹介
広瀬佳一[ヒロセヨシカズ]
防衛大学校人文社会科学群教授、秋野豊ユーラシア基金理事(事務局長兼任)。1960年生まれ。在オーストリア日本大使館専門調査員、山梨学院大学法学部助教授を経て現職
小笠原高雪[オガサワラタカユキ]
山梨学院大学法学部教授、秋野豊ユーラシア基金理事。1961年生まれ。日本国際問題研究所研究員、シンガポール大学客員研究員、北陸大学法学部助教授などを経て現職
上杉勇司[ウエスギユウジ]
広島大学大学院国際協力研究科准教授、第2回秋野豊賞受賞者。1970年生まれ。平和・安全保障研究所研究員、沖縄平和協力センター事務局長、広島大学平和構築連携融合事業研究員を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 西域余聞 朝日文庫