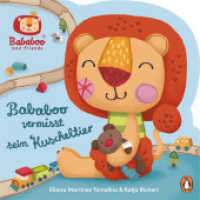出版社内容情報
幕末から明治初期に滞在した外国人カメラマン、F.ベアトが横浜・江戸・長崎など日本各地で撮影した風景、風物・風俗全236点を収録。巻末には、解説「横浜写真小史」を付す。ベアト写真集の決定版であり、幕末日本を残した貴重な史料。
ごあいさつ(高村直助[高は口がはしご])
新装版の刊行にあたって
『幕末日本の風景と人びと』の刊行にあたって(斎藤多喜夫)
[写真編]
1.横浜とその周辺
2.金沢と鎌倉
3.東海道
4.箱根と富士
5.江戸とその周辺
6.琵琶湖と瀬戸内海
7.長崎
8.風物・風俗
[解説編]
横浜写真小史 ―F.ベアトと下岡蓮杖を中心に[蓮は点が二つ]―(斎藤多喜夫)
ごあいさつ
写真には時間を止めるという不思議な働きがあります。すでに存在しない風景や人々が、写真によって、それが存在した時点で切り取られ、眼前に蘇ります。古文書が過去の社会の仕組みや出来事を伝えてくれるのに対して、古写真は人々の動作や表情、生活の舞台や環境、道具立てを伝えてくれます。それによって、歴史に対するより正確で豊かな想像力を養うことができます。
横浜開港資料館は、国際港都としての横浜が誕生する起点となった開港期を中心に、横浜の歴史資料を収集・保存・公開するための施設です。横浜では、大正12年の関東大震災や昭和20年の大空襲で多くの歴史資料が失われたため、資料を収集することは、失われた資料に代替する、あるいは補充する資料を探索し、発掘する作業をともないます。
当館では、そうした作業の一環として、開館準備の段階から、古写真の収集に力を注ぎ、日本有数のコレクションを築き上げてきました。昭和62年には、そのなかでもとくに興味深い、F.ベアトの幕末の写真を選び、「写真家ベアトと幕末の日本」という企画展示を開催しましたが、それに合わせて刊行したのが本書の前身に当たる『F.ベアト幕末日本写真集』です。
同書は刊行以降5回の増刷を重ね、約1万人の方々に購読していただきました。同書の全国普及版である明石書店の『幕末日本の風景と人びと』も3回増刷され、全国の多くの方々の手に渡りました。同書刊行以降も、当館では古写真の収集を続け、ベアトの作品もかなりの数追加することができました。そこで今年の4月26日から、新収資料を中心にベアトの作品を再度紹介する企画展示「外国人カメラマンが撮った幕末ニッポン」を開催しました。
その際、当館と明石書店とで話し合いを行い、開港資料館版と明石書店版を一本化した新装版を刊行すること、及び第2集を共同で刊行することとしました。その結果、第1集の新装版として誕生したのが本書です。『F.ベアト写真集2―外国人カメラマンが撮った幕末日本』として刊行された第2集ともども、さらに多くの読者とめぐり合えることを願っています。
平成18年6月8日
目次
写真編(横浜とその周辺;金沢と鎌倉;東海道;箱根と富士;江戸とその周辺;琵琶湖と瀬戸内海;長崎;風物・風俗)
解説編(横浜写真小史―F.ベアトと下岡蓮杖を中心に)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
punyupunyu
nizimasu
Mizhology
yossy
-

- 和書
- 対訳でたのしむ安宅