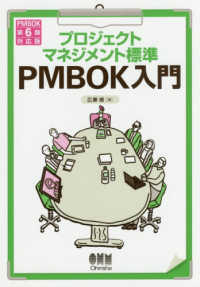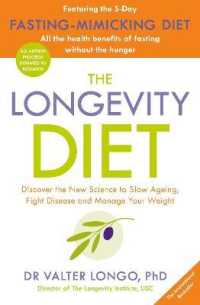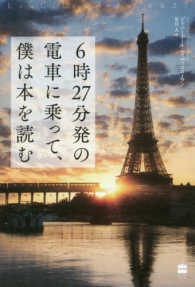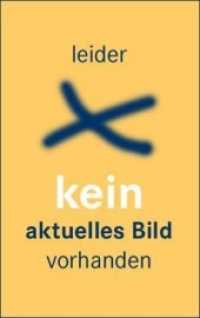出版社内容情報
OECD諸国の公務員、業績給政策を包括的に検討し、各国の業績給のメリット・デメリットを詳細に評価。有能で活力に満ちた職員の獲得と保持を目的に、民間との相異など、さまざまな問題点を各国の具体的な事例をもとに検討。付録に各国の業績給政策の全体像を把握できるよう、国ごとのデータ集を付す。
日本語版序文
序文
概要
勧告
用語集
第1章 より広範なマネジメントの文脈における業績給
1. はじめに
2. 過去20年にわたる業績給の発展
3. 業績マネジメントにおける現状の概観
4. なぜ政府が業績給を導入したのか?
4.1 モチベーションの向上
4.2 有能で活力に満ちた職員の獲得と保持
4.3 経営改革を促す
4.4 業績給は給与支出をコントロールするか?
4.5 説明責任を明らかにする
5. 業績給と人材・予算権限の委譲
6. 結論
注
第2章 OECD諸国における業績給の主要なトレンド
1. 業績給制度の全体設計における一般的なトレンド
1.1 業績給の導入はどのように、またどの程度進んでいるか
1.2 業績給政策の分権化
1.3 業績給の枠組みの分権化と権限委譲が衡平性にもたらす意味
1.4 業績給:個人別アプローチから集団別アプローチへのシフト
2. 業績評価制度:使用されている基準とシステムのトレンドを中心に
2.1 職務目標に基づく業績評価の利用拡大
2.2 業績基準として現在何が使われてい織改革の促進策としての業績給の運営
3.2.1 業績給: 目標設定政策を導入、強化する機会
3.2.2 業績給: 業務編成の変革の「てこ」
3.2.3 業績給と人材獲得
3.3 チームの業績に連動した制度は有効か?
4. まとめ
注
結論
参考文献
付録 OECD12カ国の業績給政策:概要
Boxes
図
表
日本語版序文
本書は、OECD諸国の国家公務員の給与において、業績の反映がどのように行われているか、いわゆる業績給の実態について、OECDの公共ガバナンス委員会が、加盟各国の協力を得て研究を行った結果を取りまとめた報告書である。
我が国の民間企業においては、いわゆる「成果主義」の導入が、1990年代から進んできている。この動きに対しては、近年、さまざまな議論が投げかけられてきた。昨年は、東京大学の高橋伸夫教授による、経営学の観点からの批判である『虚妄の成果主義』(日経BP社)、富士通人事部の元職員である城繁幸氏による、同社の成果主義システムの問題点を告発した『内側から見た富士通「成果主義」の崩壊』(光文社)など、成果主義に反対する論調が話題を呼んだ。一方で、民間企業における成果主義の拡大は、とどまる気配を見せない。たとえば、UFJ総合研究所の2003年10-11月の上場企業および非上場優良企業を対象とするアンケート調査では、対象企業の54%が成果主義を導入、32%が導入検討中であった(「人事制度及び人材戦略の動向に関するアンケート」2004年2月)。これが、2004年12月-2005年1月に労務行政研究所が行ったス)に成果や実績をもっと反映させる」、「民間で高い給与を支給されるほどの専門性を発揮する人材にはそれに見合った給与を支給する」を挙げている。
実際は、国家公務員の給与制度においても、本書38ページにも記載があるように、早くから業績給的要素が盛り込まれている。勤務実績を測定するための勤務評定制度は1951年から行われ、これに基づき、勤務実績に応じていわゆるボーナスを増減する勤勉手当は1952年から開始、俸給月額(民間企業でいう基本給)の昇給を勤務実績に応じて行う特別昇給は、一般職給与法には1950年の制定当初から規定が置かれ、1953年には実際に活用できるように人事院規則の改正が行われている。
では、なぜ国民の目には、国家公務員の給与は業績に依っていない、年功主義の代表例のように映るのであろうか。人事院が主宰した「地域に勤務する公務員の給与に関する研究会」基本報告(2003年7月)では、この理由を「人事評価システムについて職員団体の理解が得られなかったこともあって、持ち回りや年次順による運用に陥っているところも多い」と分析し、ボーナスにおける成績査定分の拡大が必要であるとしている。
人事評価システムにおいても、1990年代から給与と業績のリンクを強化することに挑戦してきた。この報告書では、このような先行して取り組んできた諸国の経験から、興味深い教訓を汲み取っている。たとえば、1集団別の業績給の有用性、2個人モチベーション向上効果よりもマネジメント変革・組織改革のためのツールとしての意義が大きいこと、3適切な業績評価プロセスの確立や人材マネジメントの権限委譲などの環境整備の重要性、等々である。
本報告書を取りまとめたOECDの公共ガバナンス委員会は、1990年から活動してきた公共経営委員会を前身として昨年設けられたもので、国家の公共経営に関し先進諸国政府が情報交換や研究を行う場となっている。取りまとめの中心となった人材マネジメント作業部会は、公共ガバナンス委員会でアドホックに行われてきた人材マネジメントに関するテーマを恒常的に取り扱う下部組織として、昨年から年1回定期的に開催されるようになった。我が国政府のこれらの活動への貢献は、正直なところあまり積極的とは言えない。今後は、このような貢献を拡大していくことが望まれるところであり、本書がその一助となれば翻訳に携わった者として本望である。
本報告書の翻訳、そして、本書翻訳出版の準備にあたり陰に陽に我々訳者を支援してくださった大勢の方々に、厚く御礼申し上げたい。
2005年8月
総務省人事・恩給局調査官
平井 文三
目次
第1章 より広範なマネジメントの文脈における業績給(過去20年にわたる業績給の発展;業績マネジメントにおける現状の概観;なぜ政府が業績給を導入したのか? ほか)
第2章 OECD諸国における業績給の主要なトレンド(業績給制度の全体設計における一般的なトレンド;業績評価制度:使用されている基準とシステムのトレンドを中心に;業績給:支給の形態と規模)
第3章 業績給の実施と影響:学ぶべき教訓(設計と実施に関連する問題:学ぶべき教訓;業績給のインパクト:変革のインセンティブか?)
著者等紹介
平井文三[ヒライブンゾウ]
1965年北海道生まれ。88年東京大学法学部卒業後、総務庁入庁。94年米国ジョージタウン大学公共政策大学院修了(公共政策学修士)。96年から98年まで九州大学法学部助教授(行政学)。現在は、総務省人事・恩給局調査官(給与・退職手当担当)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。