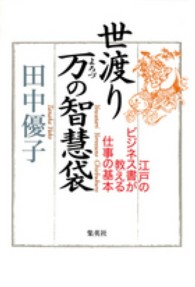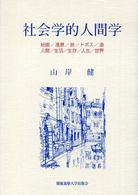出版社内容情報
イラク戦争反対のビラを自衛隊官舎に投函しただけで市民団体メンバーが逮捕され75日間もの勾留を受けた。国家が着々と戦争準備を進め、偽りの不安が蔓延する社会で、言論の自由は存在するのか。当事者の生々しい体験と各分野からの分析によって本質に迫る。
序 文 もし奴らが朝にきたら……(鵜飼 哲)
序 章 テント村とは何か
テント村小史 私たちはなぜ自衛官にビラを配るのか(加藤克子)
第1章 無罪判決までの二九四日
事件の経過 逮捕からの一年をふりかえる(井上 森)
獄中日記 壁の中で闘った七五日間(高田幸美)
公判の経過 無罪判決を勝ち取るまでの裁判審理(小島啓達)
第2章 反戦ビラ入れ弾圧とは何だったのか
座談会 イラク派兵と反戦ビラ入れ弾圧――表現の自由をどう守るか(大西章寛/寺中 誠/大沢 豊/渡辺幸之助)
対 談 自衛官に反戦を訴えるということ(大洞俊之/新倉裕史/吉田敏浩〈聞き手〉)
事件と報道 弾圧を免罪する「無罪判決」万歳報道(中嶋啓明)
第3章 法学者が見た反戦ビラ入れ裁判
裁判の意味 反戦ビラ入れ裁判で何が問われているのか(笹沼弘志)
判決の意義1 憲法 ビラ配布の自由を考える(石埼 学)
判決の意義2 刑法 三人のビラ入れは「住居侵入罪」にあたるのか(安達光治)
おわりに(大沢 豊)
巻末資料
[資料1]一月一七日に投函されたビラ
[資料2]二月二九日に出された勾留状
[資料3]
[序文]もし奴らが朝にきたら……
鵜飼 哲(一橋大学大学院言語社会研究科教授)
他の人の身に起きたことが、自分の身にも、確実に起きるべきこととして理解される瞬間がある。自分の身にも、もしかすると起きうることではなく、確実に起きるべきこととして。一九七〇年代のはじめ、アメリカ合衆国の黒人解放運動のラディカルな極を形成したブラック・パンサー党の女性弁護士アンジェラ・デービスが逮捕され、虚偽の裁判にかけられて死刑になる恐れがあったとき、作家のジェイムズ・ボールドウィンは、弾圧に抗する獄中・獄外の黒人たちの発言集の序文を次のように結んだ。
「……私たちは、あなたの命を守るために闘わなければなりません。あなたの命が私たち自身の命であるかのように。それは実際にそうなのです。私たちの体で、ガス処刑室への通路を埋めつくして通さないようにしなければなりません。なぜなら、もし奴らが朝にあなたを連れていくなら、夜には私たちを連れにやってくるからです」
「もし奴らが朝にきたら……」。この言葉は、一九七〇年代の学生運動、市民運動の活動家の間でよく知られていた。その言葉は決して海の向こうの、よその国の話としてのみ受け取らの姿を、この弾圧は私たちの目の前に突きつけた。
今回の弾圧は、イラクへの自衛隊派遣という「例外的な」時期に、自衛隊官舎という「例外的な」場所に対して行われた反戦ビラ入れ行動という「例外的な」行動に対して、反戦派の市民と自衛官およびその家族の接触・対話・交流を恐れた体制によって、「例外的な」意図のもとに発動された弾圧なのだろうか。それとも、今は「例外」であっても、いずれ改憲とともに「規則」となるべき先行的弾圧なのだろうか。私たちは今、この二つの見方が矛盾なく一致してしまう、歴史の決定的な局面に差しかかっている。
検察側の論理をたどっていけば、彼らが自衛隊官舎に対する「住居侵入」とみなした行為は、どんな集合住宅についても適用可能であることがわかる。さらには、「市民の迷惑」などという曖昧で無限に拡張可能な言い回しに訴えれば、住居に限らず、どんな空間にも適用できるようになるだろう。駅構内はもちろん、すでに多くの大学でも、構内でのビラの配布は禁じられている。公道でのビラまきがいつ禁止されても不思議ではないところまで、この社会の自由の空間は切り縮められている。
二〇〇四年一二月一六日に勝ち取られた八王子地裁のら、それ以外のことが起きた例はない。逆に言えば、「彼ら」は死ぬが「私たち」は生きられると心のどこかで信じる時、そこにはすでに、民族的、人種的な差別の「迷妄」が働いているのである。
「この国を支配する勢力にとっては、白人の生命が黒人の生命より神聖だということはありません。そのことは、ますます多くの学生が発見しつつあることであり、ヴェトナムにおける白人の死骸が証明するとおりです。……アメリカ人は、同じ都市で、同じ国土で戦われている兄弟同士の戦いが、人種戦争ではなく市民戦争だということがわかっていません。しかし、アメリカ人の迷妄は、彼らの兄弟がみな白人だと考えていることだけでなく、白人がすべて兄弟だと思っていることにあるのです」
三五年前、ボールドウィンがアメリカ合衆国内部の状況について述べたこの言葉は、「世界内戦」が語られる今日、惑星規模で妥当する。日本を支配する勢力にとって、日本人の生命がイラク人の生命より神聖だということはない。イラクで死亡した自衛官にどれほど多額の補償金の支払いが約束されていようと、この根本的な事実に変わりはない。かつてアパルトヘイト時代の南アフリカで「名誉白人」の待遇を享受していた日
内容説明
自衛隊官舎に「イラク派遣反対」のビラをまいただけで逮捕・起訴、勾留75日(アムネスティが日本初「良心の囚人」に認定)―「戦争ができる国」へと向かう社会を象徴した事件の克明な記録と分析・討論。不安が支配する社会で、私たちは何を失おうとしているのか。
目次
序章 テント村とは何か(テント村小史 私たちはなぜ自衛官にビラを配るのか)
第1章 無罪判決までの二九四日(事件の経過 逮捕からの一年をふりかえる;獄中日記 壁の中で闘った七五日間;公判の経過 無罪判決を勝ち取るまでの裁判審理)
第2章 反戦ビラ入れ弾圧とは何だったのか(座談会 イラク派兵と反戦ビラ入れ弾圧―表現の自由をどう守るか;対談 自衛官に反戦を訴えるということ;事件と報道 弾圧を免罪する「無罪判決」万歳報道)
第3章 法学者が見た反戦ビラ入れ裁判(裁判の意味 反戦ビラ入れ裁判で何が問われているのか;判決の意義(憲法 ビラ配布の自由を考える;刑法 三人のビラ入れは「住居侵入罪」にあたるのか))
巻末資料