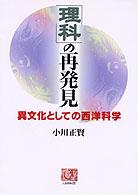出版社内容情報
「商売の民」として有名なエスニック・グループ「バミレケ」を中心に、彼らが金銭(貨幣)をいかに動かし、それによりいかなる意味や価値観を生み出しているのかを考察し、アフリカ都市の貨幣をめぐる生活戦略を提示する。
はじめに
序章
第一節 本書の目的とその論点
一 本書の目的
二 貨幣の人類学
三 アフリカ都市人類学
第二節 調査地と調査の視点
一 カメルーン共和国のなりたち
二 政治危機と経済危機
三 バミレケ
四 バミレケのダイナミズム
第三節 調査概要と本書の構成
一 調査概要
二 本書の構成
第一章 バミレケ首長制社会からの移住
第一節 バミレケ首長制社会
一 バミレケ・ランドの生活
二 首長
三 尊称とリネージ
四 貴族
第二節 移住要因とその結果
一 移住の始まり
二 農民から企業家へ
三 バミレケ・ランドにおける商人
第二章 ヤウンデへの移住と都市空間
第一節 都市のバミレケ化
一 ヤウンデの都市化
二 個人の移住軌跡
三 「土着民」の悲劇
第二節 「よそ者」としての都市生活
一 エスニック・グループと居住
二 カルチェとは何か
三 ヤウンデの首都性
四 バミレケであることの政治性
第三章 商売の経験
第一節 独立するプロセス
br> 二 都市の組織の概要
三 メンバーシップの比較
四 組織の活動の比較
五 村のタブーとトンチン
六 トンチンにおける貨幣の意味
第五章 都市居住者の生み出す「故郷」
第一節 死者祭宴にみられる消費
一 死者祭宴の重要性
二 死者祭宴のための出費
三 死者祭宴の華美さ
第二節 都市居住者が建てる村の家
一 村の家とその貸し借り
二 埋葬の場か余生の場か
三 村の家の持つ意味
第三節 新貴族とエリート
一 称号授与の決まり
二 カネで買う貴族の称号
三 エリートと貴族
第四節 ローカリティーの生産
一 リネージ長会議の変化
二 土地の商品化
三 「故郷」というローカリティー
四 「故郷」をめぐる都市居住者内の争い
終章
第一節 まとめ
一 稼ぐ
二 貯蓄する
三 投資する
第二節 考察
一 貨幣
二 都市=村落関係
三 バミレケ研究
四 今後の課題と展望
あとがき
引用文献
索引
"はじめに
本書は、アフリカ都市での現地調査(フィールドワーク)にもとづく民族誌である。アフリカ都市に暮らすひとびとが、どのように生活の基盤をたて、人間関係をつくり、故郷との関係を築くのか、そして国家政治や世界経済の流れにどのように対応しているのかを、とくに貨幣に焦点をあてながら明らかにする。
アフリカ都市といっても、たとえばそこで学校に通う子どもたちや、露天商の女性、雑貨店の主人がどのような生活をおくっているかについては、ほとんど知る機会がない。カラフルなビーズで身を飾ったマサイのひとびとや、狩猟をする「ブッシュマン」のひとびとの生活とは違って、アフリカ都市に暮らすひとびとの生活は、めったにメディアにはのらないからである。しかし、アフリカ中西部に位置するカメルーン共和国の首都ヤウンデでのべ三年暮らした筆者は、アフリカ都市の生活にも大きな魅力が備わっていると感じている。
アフリカは多様である。サハラ以南のアフリカ、いわゆるブラックアフリカだけに限っても、気候や風土、人、文化には多様性がある。アフリカ都市も同様に、長い時間をかけて人的・物的交流によって成長してきた都市や、植民地化によって短期間に建設さいるからこそ、必要とされる知恵である。自分の生活の安定や向上に役立つ出会いは、都市のどこに転がっているかわからない。人間関係のネットワークが広がれば、それだけ多くの情報やチャンスが得られる。
しかし、アフリカ都市の人間関係の濃密さは、このような「打算」だけに裏打ちされるわけではない。道端でバナナを売る馴染みのおばさんに、いつも一言、声をかける。下校中の小学生に、「しっかり勉強しろよ」とひやかす。乗合タクシーで隣のおじさんが語る不幸な身上話を聞き、一緒に嘆く。そこには、同じ都市に暮らす者同士の連帯感がある。
では、アフリカ都市で生きるとは、どのようなことなのであろうか。「生活するのは困難だ。カネ(を稼ぐこと)は困難だ(La vie est dure, l'argent est dur !)」と、ヤウンデのひとびとはよく口にする。都市では村落より多くのカネが流通し、また都市生活ではより多くのカネが必要となる。いかに収入を得、貯蓄、消費、投資するかはアフリカ都市居住者の大きな関心事であり、また死活問題でもある。
筆者がヤウンデの、外からはスラムのようにみえるアフリカ人居住区に住み始めてすぐ、まわりの人が、いつもカネの話をしていることに気ざまなアドバイスをくれた。それを素直に実行した筆者は、タクシー運転手から、「白人のくせにバミレケのようなヤツだ」と嫌味を言われることになった(しかし、こういう運転手自身バミレケであることもある)。この、多分にステレオタイプ的なエスニック・グループのカネをめぐる特徴は、政治的な話題にも発展し、「カメルーン大統領は浪費好きのベティであるから、貴重な財源をみな食ってしまうのだ。バミレケならもっとうまくやるのに」と語られたり、「反体制のバミレケは、カメルーン政府を転覆させるために、政府系銀行からカネを引き出している」などと語られる。
このように、ヤウンデという都市においては、カネにまつわるさまざまな行為や考えが日々評価され、話題になる。カネをめぐる活動が、ひとびとの都市経験の大きな部分を占めるならば、それらの活動を明らかにすることは、彼らの都市経験の大きな部分を明らかにすることになろう。都市とはすでに出来上がった所与のものではなく、そこに暮らす一人ひとりの経験が日々新たに作ってゆく空間だからである。筆者が貨幣をアフリカ都市研究の中心にしたのは、このためである。
アフリカ都市にも他の地域の都市と同様、あるいはそ"
目次
第1章 バミレケ首長制社会からの移住(バミレケ首長制社会;移住要因とその結果)
第2章 ヤウンデへの移住と都市空間(都市のバミレケ化;「よそ者」としての都市生活)
第3章 商売の経験(独立するプロセス;下積み生活としての小規模自営業 ほか)
第4章 貨幣の意味を変える貯蓄法(バミレケの「伝統」としてのトンチン;同郷会 ほか)
第5章 都市居住者の生み出す「故郷」(死者祭宴にみられる消費;都市居住者が建てる村の家 ほか)
著者等紹介
野元美佐[ノモトミサ]
1969年生まれ。総合研究大学院大学文化科学研究科修了、博士(文学)。国立民族学博物館外来研究員を経て、名古屋大学大学院文学研究科COE研究員ならびに園田学園女子大学非常勤講師。専攻は、文化人類学、都市人類学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
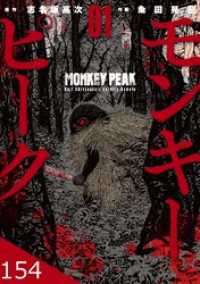
- 電子書籍
- モンキーピーク【タテヨミ】 154 ニ…