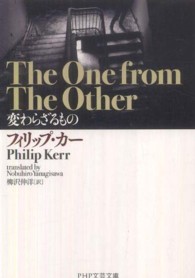出版社内容情報
在日韓国・朝鮮人の問題提起を受けて、行政の教育施策をどのように変革していったか。多文化共生の地域行政の先駆けとなった川崎市の経験と地域での多文化共生施設「ふれあい館」の誕生までを当時の行政側当事者が描き出す。
序 文
第1部 異文化受容の試み
第一章 差別構造と教育――根強い同化と排除の論理
一 戦後も生き続けた同化思想
二 在日コリアンの苦悩と日本人の眼差し
三 教育現場における変化の兆し
(1)教育行政の変化 (2)帰国子女(児童・生徒)の増加 (3)在日コリアン教育をめぐって
第二章 新しい状況の発生と葛藤
一 ニューカマーの増加が意味するもの
二 勤労青少年教育の同化と適応対策
三 地域社会における受容の今日的状況
四 外国人労働者から市民へ
五 川崎市ふれあい館の果たしている役割
第三章 川崎市外国人市民施策の展開が意味するもの
一 施策の特色と展開
二 教育施策への影響
(1)「在日外国人教育基本方針」の見直し (2)地域日本語学級の推進と街づくり (3)民族文化講師派遣事業の実施
第2部 ドキュメント川崎市桜本(一九八二~一九九〇年)――川崎市外国人教育基本方針/川崎市ふれあい館誕生のプロセス
第一章 川崎市教育委員会と川崎在日韓国・朝鮮人教育をすすめる会との話し合い
一 話し合いで提起された基本問題
(1)在日韓国・朝鮮人の「生の声青少年会館の設立要望
一 全庁的プロジェクトチームの結成
(1)民生局と青丘社による研究協議 (2)民生局から全庁的取り組みへ (3)庁内プロジェクトチームの果たした役割
第四章 ふれあい館の建設
一 行政内部での取り組み
二 地元住民への説明
(1)町内会からの施設建設要望 (2)ふれあい館建設についての地元説明 (3)町内会代表者会議
三 川崎区選出議員団との協議
四 地元町内会の反応
(1)公開質問状 (2)新聞紙上に見られた反応 (3)指紋押捺問題に関連して
五 社会福祉法人「青丘社」の対応
(1)三者協議の提唱 (2)世論の動き
六 行政と住民との話し合い――その新しい展開
(1)反対派の譲歩 (2)青丘社の見解 (3)反対住民と行政とのやりとり (4)職員派遣について新たな提案 (5)町内会役員と市との話し合い
七 ふれあい教育の成果
(1)桜本小学校の実践 (2)東桜本小学校の実践 (3)桜本中学校の実践
第五章 ふれあい館の管理運営について
一 条例制定をめぐって
(1)教育機関と福祉施設 (2)統合機能の問題点 (3)職員三章 感動体験と意味ある他者
一 マイノリティ文化が教えるもの――川崎市ふれあい館の一〇年のあゆみ
二 体験学習と精神の解放
三 異文化間コミュニケーション
第四章 人権文化の可能性
一 差別の文化と人権の文化
二 愛情のネットワーク
三 在日コリアンをべースとした施策
四 運動と実践
五 結語
資料4 川崎市の外国人市民施策の概要(一九七二~一九九七年)
あとがき
あとがき
川崎市ふれあい館が誕生したのは一九八八年六月であり、今から一六年も前の「昔」である。当時のことを思い起こし、施設建設のプロセスを語ることに今日どれだけの意味があるのか、正直いってよくわからない点もないわけではない。
しかしこの拙いものを著そうと決意したことは、次のような理由からである。
その第一は、このような機能と役割をもつ施設が求められているにもかかわらず、全国的にもまだ生まれていないこと。さらにその背景にある教育・福祉施策確立の経緯、そして外国人とりわけ在日韓国・朝鮮人市民と行政が一体となって進めたコミュニティづくりなどの事実を今こそ公にする必要がある、との助言を親しい人々からいただいたことである。
その第二は、一〇年ほど前に故岩淵英之元川崎市教育長からこの記録を「まとめて出版したらどうか」と言われていたことが常に脳裡をかすめていたことである。
その第三は、私は二〇〇三年に四二年間世話になった川崎市を離れて、雪国新潟は魚沼の地で生活している。川崎市職員として後半の一七年間(一九八二~一九九九年)はふれあい館に学び、その実践と行動に支えられて行政の仕事に従事してきたといっても過しい地平を拓くことも可能であるし、事実このことに成功した例も少なからず存在するものと思われる。
この地域で試みられた共生の街づくりは時間の経過とともに新たな課題にも遭遇しているはずである。新来外国人と住民との新しい関係づくりが在日韓国・朝鮮人の問題とどうリンクしているか、その異同をめぐってどのような論議が展開され、実践に移されているかということも興味を引く点である。
それにしても「差別の実態をみとめる」ことが人々にとって、とりわけ行政関係者にとって難しく、大変なことかということをしみじみと感じている。と同時にこれを素通りにしては人権思想の普及も発展もそして定着も不可能であることを痛感している。
二一世紀は人権の世紀であると声高に語られているが、これを本格化するためにはこれまで以上の努力が日常的に払われなければならないだろうし、そのことが新しいコミュニティ形成の礎になることはほぼ間違いないように思われる。(後略)
目次
第1部 異文化受容の試み(差別構造と教育―根強い同化と排除の論理;新しい状況の発生と葛藤;川崎市外国人市民施策の展開が意味するもの)
第2部 ドキュメント川崎市桜本(一九八二~一九九〇年)―川崎市外国人教育基本方針/川崎市ふれあい館誕生のプロセス(川崎市教育委員会と川崎在日韓国・朝鮮人教育をすすめる会との話し合い;基本認識から基本方針へ;青少年会館の設立要望 ほか)
第3部 多文化主義と人権文化(多文化主義を阻むもの―差別文化の実態;学校文化と同化政策の克服;感動体験と意味ある他者 ほか)
著者等紹介
星野修美[ホシノオサミ]
1938年新潟県生まれ。61年東洋大学社会学部社会学科卒業。1961~99年川崎市職員(主な職歴―社会教育主事、青少年課長、国際室参事、市民文化室長、教育文化会館館長)。日本女子大学人間社会学部、東洋大学大学院社会学研究科、東京都立大学人文学部各非常勤講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。