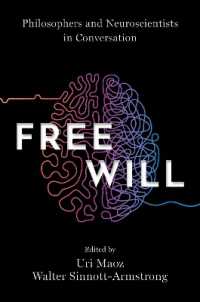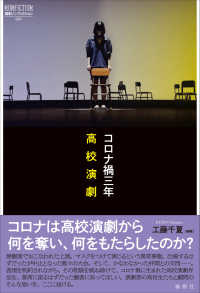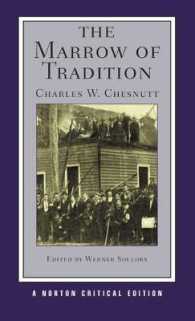- ホーム
- > 和書
- > 社会
- > 社会問題
- > 社会貢献ボランティア
出版社内容情報
北東アジアの平和的共生のため、北朝鮮をめぐる市民サイドの人道支援のあり方や交流活動の役割をJVCの活動、韓国の運動を通して考える。また在日コリアン、朝鮮学校生徒が抱える現状に対する不安など、現場に携わる11人の筆者がレポートする。
この本をお読みになるみなさんへ (武者小路 公秀)
はじめに/Foreword
一 北朝鮮人道支援をめぐる日本のNGOの経験 (金 敬黙)
1 北朝鮮問題と政治的中立性/2 食糧危機の発生と日本政府の人道支援/3 日本のNGOの活動/4 活動の意義と限界
二 国際協力型NGOの経験――世界の紛争と北東アジアの平和 (熊岡 路矢)
1 世界の根本問題/2 人道の問題/3 JVCによる人道支援/4 実働型NGOの役割/5 北東アジアの平和と人道支援問題
三 北朝鮮人道支援の「難しさ」と「対話」 (筒井 由紀子)
1 自由に写真が撮れない/2 行きたいところへ行けない?/3 現地に駐在する国際機関、NGOの考える「難しさ」/4 日本のNGOの考える「難しさ」――調査が先か? 支援が先か?/5 日朝間の「距離」/6 「日朝首脳会談」の影響/7 「対話」は不可能?/8 子どもたちとつながりたい――ルンラ人民学校/9 協同農場で……
四南北コリアと日本のともだち展――人道支援NGOがすすめる交流 (寺西 澄子)
コラム1/1966年の北朝鮮と英国 Try to Paint a Different Picture (宋 幸洙)
五 過去を越えた多文化共生社会へ――在日朝鮮br>八 「日朝首脳会談」と在日コリアン (金 聖蘭)
1 「日朝首脳会談」の夢と現実/2 民族と国家の狭間で/3 メディアがつくる北朝鮮像/4 教師として、在日コリアンとして
付/北朝鮮をめぐる国際情勢と「KOREAこどもキャンペーン」のあゆみ(1993-2003)
あとがき
はじめに
本書は、日本国際ボランティアセンター(以下JVCと略す)のコリアチームが2002年度活動の一環として行った調査研究プロジェクトの成果である。調査研究活動は「北東アジアの平和的共生―DPRK(北朝鮮)をめぐる市民社会の役割」というテーマで実施された。プロジェクトは、日本と韓国を拠点とするNGO活動者、メディア関係者、研究者、教育機関関係者などの参加を得て、学際的な研究活動と実践活動が実施された。
北東アジアを取り巻く諸問題を、日本と韓国の市民社会が地域の共通課題として解決する新しい試みであった。日本と韓国の市民社会がネットワークを形成する活動は決して新しいものではない。しかし、90年代半ば以降、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)で発生した人道危機問題に日韓の市民社会が協力を展開するというアプローチは、地域の平和的共生を目指す新しい展開であると理解している。
そして、本書は、JVC関係者をはじめ、調査研究プロジェクトに協力してくださったメンバーたちの視点に基づいて構成されている。90年代半ば以降から展開されてきた対北朝鮮人道支援活動は、日本と北朝鮮、南北コリア、その他、北東アジアの地政学的情勢教育現場へいかに適用されうるのかという教訓を模索している。そして、八章では、日本と北朝鮮の間で生じる政治問題のはざまで苦しむ在日コリアンの心境を扱っている。また、本書中の四つのコラムは、共生社会・平和文化の創造に関わる活動の事例を紹介したものである。(後略)
内容説明
本書は、日本国際ボランティアセンターのコリアチームが2002年度活動の一環として行った調査研究プロジェクトの成果である。調査研究活動は「北東アジアの平和的共生―DPRK(北朝鮮)をめぐる市民社会の役割」というテーマで実施された。プロジェクトは、日本と韓国を拠点とするNGO活動者、メディア関係者、研究者、教育機関関係者などの参加を得て、学際的な研究活動と実践活動が実施された。
目次
1 北朝鮮人道支援をめぐる日本のNGOの経験
2 国際協力型NGOの経験―世界の紛争と北東アジアの平和
3 北朝鮮人道支援の「難しさ」と「対話」
4 南北コリアと日本のともだち展―人道支援NGOがすすめる交流
5 過去を越えた多文化共生社会へ―在日朝鮮学校の存在と民族教育実践の意味(抄訳)
6 韓国の平和運動と平和教育(抄訳)
7 越境する平和教育―南北オリニオッケドンムに学ぶ
8 「日朝首脳会談」と在日コリアン
付 北朝鮮をめぐる国際情勢と「KOREAこどもキャンペーン」のあゆみ(1993‐2003)
-

- 和書
- 生命の劇場