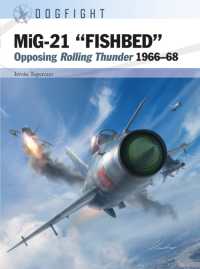出版社内容情報
子どもが育つ本来の姿がみえてこない時代である。それどころか、子どもたちは社会変動の波に翻弄されている。その中で、子どもの福祉文化を拓くさまざまな実践がおこなわれている。それらの実践から、これからの展望を探る。
刊行の言葉 (一番ヶ瀬康子)
序 子どもの権利条約と福祉文化 (一番ヶ瀬康子)
第1部 子どもと福祉文化
第1章 良寛さんやエレン・ケイに学ぶ子どもと福祉文化 (小沼肇)
第2章 福祉文化を考えるために
1 子どもの福祉文化の基盤――豊かな自己実現のために (山田美津子)
2 子どもの暮らしと家庭・地域――日々生きることを学ぶ (阿部祥子)
3 子どもの暮らしと教育――心の声を理解する (大島道子)
4 子どもの暮らしと商業化――消費文化とその病理 (田中利則)
5 子どもの暮らしと情報化・国際化――メディア時代の子どもたち (月田みづえ)
第2部 子どもの福祉文化を拓く
第1章 “わんぱくっ子 ばんざい”――子どもたちの活動を支える
1 冒険遊び場――〈羽根木プレイパーク〉の実践 (嶋村仁志)
2 子どもたちが主役――〈ゆう杉並〉の実践 (福田惠美子)
第2章 “ひとりでがんばらないで”――SOSを発信する子どもたちを支える
1 子どもたちの可能性――スクールソーシャルワーク (山下英三郎)
2 子どもたちの助け合い活動――チャイルドライン
刊行の言葉 日本福祉文化学会会長 一番ヶ瀬康子
福祉は、文化である。福祉は、人間の歴史が始まって以来、幸せを願い、求め、祈りつつ、次第に創造されてきた。そして前世紀には、社会福祉制度としての領域を確立し、それは人権としてとらえられるようになってきた。少子高齢化の進む二一世紀には、社会福祉領域のいっそうの拡大とともに、その地域化、国際化が進むであろう。その福祉の社会的拡がりに、文化の薫り高い内容をもりこみ、創造性をさらに高めることが、現在いっそう求められているのではないだろうか。
以上の想いと願いで、一九八九(平成元)年に創設した日本福祉文化学会は、社会福祉の現場とともに、福祉文化のボランタリーな市民活動を高めることを務めてきた。本シリーズでは、その実践事例を紹介し、学会員の所見を編集したものである。
このシリーズ刊行を機に、平和で心豊かな二一世紀の福祉文化の創造に対し、多くの人々の共感と、一層の努力そして連帯が生まれることを願ってやまないしだいである。
二〇〇一年五月三日
内容説明
一九八九(平成元)年に創設した日本福祉文化学会は、社会福祉の現場とともに、福祉文化のボランタリーな市民活動を高めることを務めてきた。本シリーズでは、その実践事例を紹介し、学会員の所見を編集したものである。
目次
序 子どもの権利条約と福祉文化
第1部 子どもと福祉文化(良寛さんやエレン・ケイに学ぶ子どもと福祉文化;福祉文化を考えるために)
第2部 子どもの福祉文化を拓く(“わんぱくっ子ばんざい”―子どもたちの活動を支える;“ひとりでがんばらないで”―SOSを発信する子どもたちを支える;“輝く子どもたち”―育ちを支える、学びを支える;“子どもの宝物”―子どもの文化の伝承と創造;“ここなら安心”―すべての子どもと家庭を支える)
第3部 今後の展望(すてきな子どもたちに明るい未来を)
著者等紹介
一番ヶ瀬康子[イチバンガセヤスコ]
長崎純心大学教授・日本女子大学名誉教授。日本福祉文化学会会長
小沼肇[コヌマハジメ]
静岡英和学院大学教授。日本福祉文化学会理事
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。