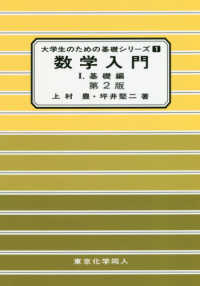出版社内容情報
漢字の伝来によってその姿を覆い隠されてしまった大和言葉。その大和言葉の姿を古代人の社会・生活様式を通じて明らかにし、さらに「君が代」の本来の意味を大和言葉から読み解く。
第一章 はじめに
言葉は共有体験/「こころ(心)」と「からだ(身体)の意味は/「つみ(罪)」を定めた外来語「ばつ(罰)」/「つむ」から生まれる「とも(友・共)」/定住を促す「かわ(川)」と住まう場所を意味する「しま(島)」/船の大和言葉が明らかにする三種の区分/士器についての三種の区分/古墳についての三種の区分/「こめ(米)」についての三種の区分/古代を明らかにする「かばね(姓)」という言葉/「う(余剰)」を作る集団「うぢ(氏)」/ほか
第二章 「君が代」を読み解く
「君が代」を教えることができるか?/「いし(石)」の意味を忘れた日本人/「いし」の意味を明らかにする「いさ・いざ」/「いわお」は「いはほ」で「巌」ではない/「きみ(君)」は天皇を意昧しない/「きみ(君)」は「かみ(神)」を仲立ちするひと/「おおきみ(大君)」は「きみ(君)」を生み出すひと/「よ(代)」とは何か?/「ちよ・やちよ」は「千代・八千代」にならない/「さざれいし」とは大和言葉を知らない人の理解/「巌や苔」の意味する奇妙さ/ほか
第三章 「かばね(姓)」を読み解く
曖昧にされてきた「くに」という言葉/「みやこ(都)」火の獲得と森からの脱出/移動生活を示す旅や「行く」/「しま」の発見=移動から定住ヘ/「こち(東風)」はこちらに吹く風?/南として「はえ」、北は「いにし」/人類史の第二の変化点とは定住生活/定住をもたらす土器としての「なべ」/定住を促す「なひ→なへ」と「ほへ」、「あき(秋)」の原義は収穫/「かばね(姓)」の登場と大和言葉の変容
第六章 仏教による大和言葉の変化
瓦葺として登場する「てら(寺)」/法と罰とを持ち込んだ仏教/死は外来語/「悟り」にひそむ「死のさだめ」/定住農耕を促す「穢れ」概念/独自な過去を奪う外来宗教/まだまだ続く宗教の支配
第七章 おわりに
言葉でさぐれる歴史の転換点「移動から定住」/関わりを示す大和言葉/関わりを無視する翻訳語/言葉の宝庫=大和言葉/人を意味する「ち」?/美しい言葉「ちゆ=美」
目次
第1章 はじめに(言葉は共有体験;「こころ(心)」と「からだ(身体)」の意昧は ほか)
第2章 「君が代」を読み解く(「君が代」を教えることができるか?;「いし(石)」の意味を忘れた日本人 ほか)
第3章 「かばね(姓)」を読み解く(曖昧にされてきた「くに」という言葉;「みやこ(都)」は「くに」を「あがた(県)」と「こおり(郡)」に分かつ ほか)
第4章 身体言語が出発点(「いへ(家)」と個人の関係を示す身体言葉
「あたま(頭)」は「あつむ(集む)」から ほか)
第5章 大和言葉で歴史をさかのぼる(外来語(漢語)を取り入れるための文体こそ日本文の構造
火の獲得と森からの脱出 ほか)
第6章 仏教による大和言葉の変化(瓦葺として登場する「てら(寺)」
法と罰とを持ち込んだ仏教 ほか)
第7章 おわりに(言葉でさぐれる歴史の転換点「移動から定住」;関わりを示す大和言葉 ほか)
著者等紹介
長戸宏[ナガトヒロシ]
徳島県生まれ。名古屋工業大学卒
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。