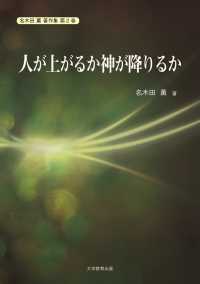出版社内容情報
たとえば相手の容姿を見て、先入観や価値観に基づき認識して接する。そこからたち現れる言葉や態度を、相手は「まなざし」として感じとり、自己を形成していく。この「まなざし」論は、哲学をはじめとする、さまざまな領域で論じられてきたが、日本語教育の場では見落とされてきたのではないか。日本語教師である著者は、日本に一度も住んだことのない子どもや、来日した子どもたちが抱える課題に対面し、子どものことばの学びと「まなざし」がどのようにかかわっているのかを考察する。著者自身の論文やエッセイを二次分析し、「まなざし」の形成過程をたどることで、見えてくるものとは。オーストラリアの日本語教室における、教師や保護者が自己省察を行った事例も紹介する。
内容説明
わたしたちは子どもをどのように見て実践しているのか。子どもたちは周囲のさまざまな「まなざし」の中でことばの学びにいたったりいたらなかったりしているのである。複数言語環境で成長する子どもがおかれた社会的文脈に寄り添うには「見る・見られる」という観点からの議論は不可欠である。(本書より)
目次
第1部 子どもの日本語教育における「まなざし」論(子どもの日本語教育においてなぜ「まなざし」を語るのか;「まなざし」に関する先行研究と日本語教育;複数言語環境で成長する子どもの日本語教育に関する先行研究;研究方法;対象化する「まなざし」;客体化する「まなざし」;相互主体の「まなざし」;総合考察―「実践者」の「まなざし」の形成過程;「まなざし」の観点から再考する子どもへの日本語教育実践の意義)
第2部 「まなざし」の観点から未来を紡ぐ実践へ(親子の「ことば育て」という日常実践;あおぞら食堂の挑戦)
著者等紹介
中野千野[ナカノチノ]
福岡県生まれ、佐賀県育ち。2016年9月、早稲田大学大学院日本語教育研究科博士課程修了。博士(日本語教育学)。2017年よりオーストラリア在住。大学卒業後、テレビ局勤務を経て日本語教師に転身。1997年より国内外の日本語学校、大学、企業の日本語教育に携わる。現在はオーストラリアで子育てをしながら、子どもへの日本語教育に従事。在野の研究者としても子どもへの日本語教育を中心に実践研究活動を行っている。第7回スミセイ女性研究者奨励賞:研究テーマ「複数言語環境で成長する子どもの主体性を生かす日本語教育の研究―ライフストーリーの相互構築過程に着目して」。2008年度第3回博報「ことばと教育」研究助成:研究テーマ「多文化共生を目指した特殊目的の日本語教育支援への提言」(研究助成番号:08-A-0007)研究代表者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。