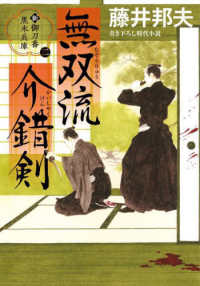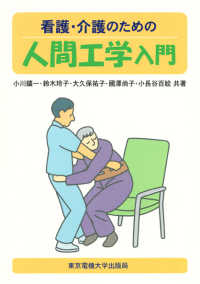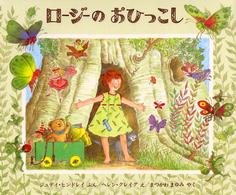内容説明
金沢大学在職中(1959‐1969)の著者の研究のまとめ。
目次
第1章 「新教育」の胎動と帝国主義への志向
第2章 帝国主義と教授・訓育の改造
第3章 「新学校」の設立とそこでの教育
第4章 デモクラシーの潮流と教育改造
第5章 自由教育運動の展開
第6章 国家権力と自由教育
第7章 大正自由教育の遺産と歴史的役割
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
てれまこし
3
国家が望む知識と道徳を一方的に詰め込む容器としてしか子供を見ない明治教育に対して、子供を学ぶ主体として捉えなおそうと現場の教師たちが叛乱を起こす。忠良臣民を育てるだけじゃなくて、全人格的な陶冶を目指す。背景には大正デモクラシーがあり、資本主義の成熟に伴い厚くなった中流階級が支持層となった。それ故に限界もあり、ブルジョアのおぼっちゃま教育との批判も免れない。早くも1920年代後半には保守派からも左派からも叩かれ衰退していく。息子を成城に送り出した柳田も賛同していたらしく、その教育観に通ずるところが多々ある。2019/01/14