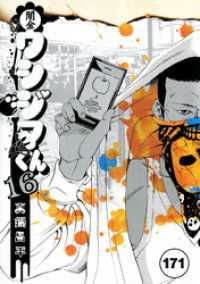出版社内容情報
日本文化は、独特の自然環境によって形成された基層文化の上に、大陸より漢字・仏教・儒教などを受容し、さらにヨーロッパ文化が伝来することで重層的で複雑な構造を持つことになった。神話の時代から現代に至る思想・宗教・文学・芸能など幅広い事象を講義形式で解説。文化史の時代区分に一石を投じ、今後の歴史研究のあり方に問題を提起する。
内容説明
独特の自然環境によって形成された基層文化の上に、外来文化を受容することで重層的な構造を持った日本文化。思想・宗教・文学・芸能など、幅広い事象を講義形式で解説。その複雑な性格と、豊かな内容を明らかにする。
目次
1 日本の文化と思想(日本文化の見方;神々の祭りと日本神話;仏教の伝来と受容 ほか)
2 文化史の時代区分(時代精神と文化史;文化の諸分野とその歴史;部門史を総合する試み ほか)
3 史料としての文学作品(歴史研究と文学作品;「文学作品」について;史料としてのあり方 ほか)
著者等紹介
大隅和雄[オオスミカズオ]
1932年、福岡県に生まれる。1955年、東京大学文学部国史学科卒業。東京女子大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。