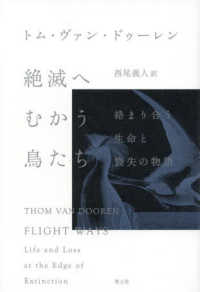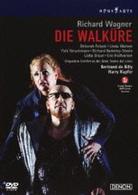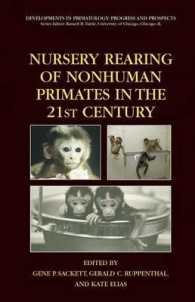出版社内容情報
古来、人々の生活と深く結びついている暦。日本史を理解する上で、暦の知識は欠かせない。その誕生や太陽暦・太陰暦などの基本事項をはじめ、中国から導入・運用された暦の歴史を詳述する。また、日食・月食などの天体現象や年中行事
内容説明
暦のはじまり、日食・月食、二十四節気、陰陽師…。古代の暦の知識が身につくとっておきの入門書!
目次
1 暦とは何か(人間にとっての暦;太陽暦と太陰暦)
2 古代日本の暦史(日本列島における暦の始まり;律令国家と暦;暦道賀茂氏の成立―造暦組織の形成)
3 暦をめぐる習慣(貴族と暦;暦注の種類;都城と方違えと陰陽道;暦と天体現象)
著者等紹介
細井浩志[ホソイヒロシ]
1963年千葉県に生まれる。1994年九州大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。現在、活水女子大学文学部教授。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koning
25
歴法の紹介と基礎的なところから日本で使われた各種歴法とその影響をざっと(といいつつ結構細かく)解説してくれてます。イスラーム歴の解説もあったりして(現役だもんね)歴法の面倒くささの一端が垣間見えてよござんす。ただ問題は1度じゃぁ腑に落ちない(笑)。時々読み返すことになるだろーなという感じ。東洋史はスルーに近いのでなかなかいろいろと新鮮でござんした。2015/04/29
みつ
21
およそ半世紀お付き合いいただいている、高校・大学のサークルの先輩からお借りした本。暦については一定の興味があり、17世紀江戸の貞享暦作成が主題の小説『天地明察』も堪能した身としては、それまで長く用いられた、9世紀の宣明暦までの暦について、政治との関わりも交え記述され、難解ではあっても面白い。特に興味があったのは、①月は忌むべき存在なので、月のない朔(さく。新月)が月の始まりになった(p64の趣旨)、②古代中国では地球が球体であることを知らなかった(p115)。暦に記される各種記載の解説も学ぶことが多い。2026/01/03
俊介
16
歴史学者が書いた旧暦の本。なので歴史的な話がメインだが、本書が有能なのは、旧暦の複雑な仕組みについても、図や表を用いてかなり丁寧な解説がなされているとこだ。もはや完全に理系分野。複雑だけど、旧暦(太陰太陽暦)はほんとよく出来てる。1年という単位は太陽の周期(太陽暦)で計算し、1か月という単位は、月の周期(太陰暦)により計算する。太陽の1年と月の12か月は長さが微妙に異なるので、リンクさせるには、高度な計算力と天体観測技術が必要になるのだが、古代人は見事やってのけた。計算機や望遠鏡も無い時代に。古代人凄すぎ2021/11/12
赤白黒
3
知っているようでいて、実は全然知らない暦の話。世界各地の暦の起こりから筆を起こし、図版を多用して天体の運行等の説明も多くなされているので、古代の天文学に興味がある方にもお勧め。太陰太陽暦については恥ずかしながら閏月の置き方など初めて知ったのでとても勉強になった。歴史書を読むのがますます楽しくなりそう。天文の読み解きが生活の安寧に直結する時代のこと、必死にならざるを得なかったのだろうが、古代人の叡智はすごい。余談だが、「桓武天皇が日食記事を削除させた(大意)」とあり、ここでも桓武天皇かと苦笑してしまった。2024/09/14
さとうしん
3
「日本史を学ぶための」とあるが、太陽暦に関しては古代エジプトやローマの、太陰太陽暦に関しては中国の状況に触れるなど、広く暦や天文に関する入門書となっている。2014/08/25