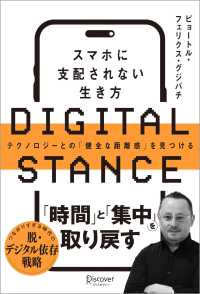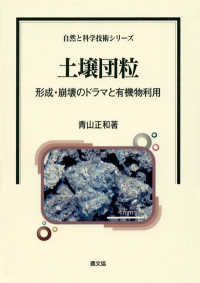内容説明
目に見えない霊物が、貴族たちの日常を脅かす。彼らは陰陽師に何を求めたか。生活文化のなかの陰陽師という視点で平安時代を再考する。陰陽道と生活の関係が浮き彫りにする、日本独自の文化=国風文化のもう一つの姿。
目次
平安貴族と陰陽師の世界へ
1 家宅を鎮める(新宅作法の次第;宅神と陰陽師;土公神と陰陽師;家宅の危険性と陰陽師の反閇)
2 病気を癒す(普通の病気と陰陽師;神の祟と陰陽師;仏の祟と陰陽師;霊鬼と陰陽師;疫病と陰陽師)
「安倍晴明」と「歴史民俗学」―結びに代えて
著者等紹介
繁田信一[シゲタシンイチ]
1968年東京都に生まれる。2003年神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科博士後期課程修了。現在神奈川大学日本常民文化研究所特別研究員、同大学外国語学部非常勤講師、博士(歴史民俗資料学)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
12
陰陽師それ自体ではなく、「陰陽師がいる風景」としての平安貴族社会に焦点を合わせた一冊。貴族たちはなぜ陰陽師を必要とし、何を期待していたのか。神秘的なイメージを排し、日常生活の中で陰陽師が果たした機能を淡々と説明していく姿勢が好ましい。実際、彼らが活躍したのは怨霊との戦いなどエマージェンシーな局面ばかりではない。例えば引っ越しや家の新築に際して適切な助言を行い、段取りをつける。地味だが社会生活に欠かせない存在。陰陽師を知ることは、平安貴族の心性を知ることでもある。2024/10/12
かっぱ
3
藤原道長の「御堂関白記」などの文献から、陰陽師と平安貴族の生活が切っても切れない関係にあったということがわかる。病気の治療にあたっては、医師、験者、陰陽師がそれぞれ役割分担していたというのがおもしろい。陰陽師の存在が現実味を帯びて感じられるようになった。また、当時は清明を「セイメイ」とは呼んでいなかっただろうとの記述にも興味を持った。「ハルアキ」「ハルアキラ」「ハレアキラ」のどれかではないかとのこと。2011/07/03
momen
1
安倍晴明はじめ陰陽師が公的に活躍していた時代、平安貴族が陰陽師をどのような場面で使っていたかの解説本。陰陽師・仏教僧・医者の使い分けや、引っ越しや空き家のお祓いの作法など、平易な記述で分かりやすくまとめてある。内容はしっかり昔の記録に基づいているものだが、語り口はライトな感じで読みやすい。まだ科学が未発達で霊的なものへの恐怖心が強かった時代、貴族たちは何をどのように解釈し恐れていたのかの一端が見える。「晴明」の読み方についての説明も面白い。2022/12/04
たらら
1
古記録にきちんとあたり、陰陽師と平安の時代の信仰のあり方を的確に捉えてみせる丁寧さと誠実さはよいが、ダイナミスムも大胆さもなく、この著者の仕事としては試論にすぎないという感じ。2011/09/09
幽寂庵
1
陰陽道の変遷を辿る。さらっと読めますので初心者向け。2009/06/30