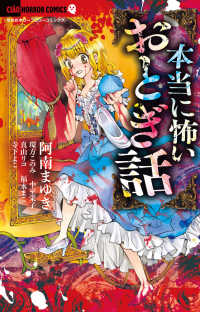内容説明
現代では、農の機能として、食料の生産だけでなく、自然環境や景観の保持、地域文化の継承なども求められている。都市においては食の問題と直結し、さまざまな農の試みがなされている。食と農の民俗的意味を追究する。
目次
くらしと食農(環境問題と農―新たな農の取り組み;農にみる伝統への回帰;食と農の未来)
1 自給と食のイデオロギー(「自給」と社会;都市化と農村自給の意義;戦争と国民的自給;反動としての「自給の思想」;現代社会と「自給作物栽培」)
2 農のいとなみと労働(農と民俗学;手植え/正条植の導入;手植え/正条植の展開;機械植/正条植と農の意味の変化;再び農と民俗学)
3 農のあるくらし(市民生活と農;市民農園のいとなみ―『市民農園記録』から;農と農村の変化―昭和三〇年代の意味)
著者等紹介
安室知[ヤスムロサトル]
1959年、東京都に生まれる。1985年、筑波大学大学院環境科学研究科修士課程修了。現在、国立歴史民俗博物館教授、総合研究大学院大学教授(併任)
古家晴美[フルイエハルミ]
1960年、神奈川県に生まれる。1993年、筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。現在、筑波学院大学准教授
石垣悟[イシガキサトル]
1974年、秋田県に生まれる。2001年、筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科退学。現在、文化庁文化財部伝統文化課文部科学技官(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
1
「日本の農業を考えるとき、とくに中山間地域においては、過疎・高齢化は避けて通ることはできない。しかし、農は中山間地域でのみおもkなわれるわけではなく、(略)過疎・高齢化を日本農業の弱点、さらに民俗学においては伝承母体の消滅と捉え、はじめからマイナスイメージに押し込めてしまうことは誤りである」(278ページ)。その通りだと思う。積極的撤退論の農村計画学も存在するが、民俗学の土着研究からもう一度新たな価値を再創造していくことも重要だろう。そのためには、林直樹先生の種火集落を再燃、活性化させる方向性も重要だ。2012/11/11