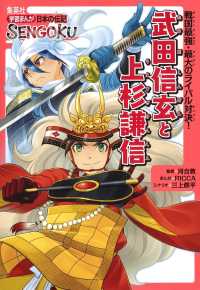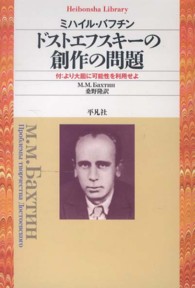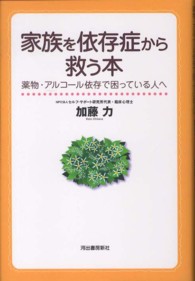内容説明
みちのく平泉に黄金と浄土の都を築いた奥州藤原氏。東北最強の武士は、なぜ浄土を求め、そして滅んだのか。繰り返された戦争、都市平泉の実像、義経の亡命など、東北の風土とともに生きた四代一〇〇年の物語を再現。
目次
1 奥州藤原氏四代の履歴書(初代清衡;二代基衡;三代秀衡;四代泰衡)
2 都市平泉の実像(都市の「顔」;御館の住む平泉館;平泉の「かたち」と「くらし」)
3 奥州藤原氏の戦争(前九年合戦;後三年合戦;奥州合戦;平泉の滅亡)
4 奥州藤原氏の平泉を歩く
著者等紹介
岡本公樹[オカモトコウキ]
1972年神奈川県横浜市生まれ。慶應義塾大学文学部東洋史学科専攻卒業後、1995年読売新聞入社。福島支局、社会部、東北総局、文化部・歴史文化財担当などを経て、現在、金沢支局次席(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
三谷銀屋
2
東北の覇者であった奥州藤原氏4代の興亡の百年史をざっくり俯瞰できる一冊。東北の一大勢力でありつつも、百年に亘り中央政権との微妙な力関係のバランスに運命が左右されてきた歴史が印象的。摂関家が日記で藤原基衡を「匈奴」と蔑称したと書かれているけど、確かに、古代中国に対する遊牧騎馬民族の関係を連想させる部分もあるように感じた。平泉は思っていた以上に豊かで大きな都市だったようで、鎌倉幕府の代わりに、奥州藤原氏が実権を握る「平泉幕府」が成立した可能性も、歴史のifとしては充分ありえたのかもしれない、と思った。2020/03/15
へたれのけい
2
たまには地元の本を読もうと手にしました。 三代秀衡が長生きをして、義経を立てて頼朝と戦ったなら…。とか色々空想してしまいます。でも、義経をジンギスカンにした先人のたくましい想像にはとても及びません。2014/05/17
Taq Asaq
2
平泉について、お手軽に学ぼうと思って手に取ったら、なかなか簡潔によくまとまっていた。それはさておき、作者の人が、うちの会社の部署の先輩だった(同じ時に在籍していないので、直接知り合いではない)。さすがに30代も半ばになると、書物を世に問うている人が、友人知人に何人も出てきている。ううむ。俺もがんばらないといけないなあ、盛岡で冷麺食って喜んでる場合じゃないよなあと思う次第でした。まったく本の感想ではなくなってしまった。。。2014/05/12
Go Extreme
1
平泉―黄金と浄土の都 奥州藤原氏四代の履歴書: 初代清衡 二代基衡 三代秀衡 四代泰衡 四代の死亡診断書 都市平泉の実像: 都市の「顔」 御館の住む平泉館 平泉の「かたち」と「くらし」 平泉と浄土信仰 奥州藤原氏の戦争: 前九年合戦 後三年合戦―正統はだれか 奥州合戦/平泉の滅亡 奥州藤原氏の平泉を歩く: 中尊寺と金色堂 色堂 聖なる里山、金鶏山 毛越寺―現世に現れた浄土世界 夕日の沈む光あふれる無量光院 ニュータウン「衣川」北岸 平泉の地名の由来は2024/09/27
うしうし
1
文章が平易で理解しやすいことが本書の特徴。これは著者が歴史研究者ではなく、新聞社に籍を置くジャーナリストであるためか?しかしながら、その内容は近年の研究成果の紹介に留まり、著者の独自見解や歴史観は描かれていないように思う。また、このシリーズ全般にいえることだが、カラー用の上質紙で作られているにもかかわらず、図版よりも文章の方が目立ち、挿図にしてもよく知られた写真や適当な地図を着色したものが提示されているに過ぎない。本の装丁を活かして、もう少し踏み込んだ工夫のあるものにして欲しかったというのが正直な感想。2015/05/13