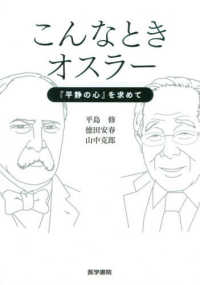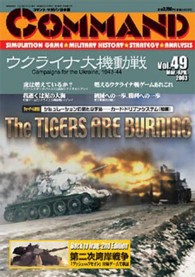出版社内容情報
ドストエフスキー論の初版。筆を矯めざるを得なかった増補改訂版(『詩学の問題』)より率直で明確な対話論・ポリフォニー論が展開される。バフチン言語論の中心思想を把握できる待望の初訳!
内容説明
言葉はつねにすでに他者の言葉への応答としてある―独自の言語理論・文学論は、ドストエフスキー作品を場にポリフォニー論という結晶をもった。カーニヴァル論などを加えただけでなく、編集部の要求などにより変更され、『詩学の問題』と改題された増補改訂版ではなく、そのオリジナル版『創作の問題』こそ、バフチンの理論の核心がより率直に鮮明に語られる。待望の初訳。
目次
第1部 ドストエフスキーのポリフォニー小説―問題提起(ドストエフスキーの創作の基本的特徴と、批評文献におけるその解明;ドストエフスキーにおける主人公;ドストエフスキーにおけるイデー;ドストエフスキーの作品における冒険的プロットの機能)
第2部 ドストエフスキーにおける言葉―文体論の試み(散文の言葉の類型。ドストエフスキーにおける言葉;ドストエフスキーの中篇小説における主人公のモノローグ的言葉と語りの言葉;ドストエフスキーの長篇小説における主人公の言葉と語りの言葉;ドストエフスキーにおける対話)
著者等紹介
バフチン,ミハイル[バフチン,ミハイル] [Бахтин,М.М.]
1895‐1975。独自の言語理論に立脚した文学・文化研究によって、世界的に大きな影響を与えるロシアの思想家。1920年代から、講演会・講習会を通じて、いわゆるバフチン・グループが形成され、このサークル仲間の名義で言語学、哲学などに関する著作を発表、1929年には本人名義で『ドストエフスキーの創作の問題』を刊行、また1930年代には『小説の言葉』を含む一連の小説論を執筆、ラブレー研究にも着手し40年に論文を書き上げたが、それらの仕事は十分に価値を認められなかった
桑野隆[クワノタカシ]
1947年、徳島県生まれ。早稲田大学教育学部教授。専攻は、ロシア文化・思想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
Pustota
壱萬参仟縁
有沢翔治@文芸同人誌配布中
Bevel