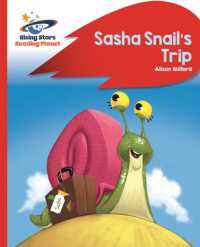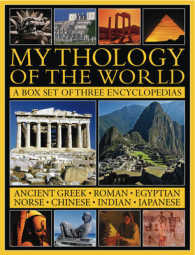内容説明
ポツダム宣言を受諾、再出発した“敗者”日本。軍国化への道と太平洋戦争の敗北から何を学ぶことができるのか。最新の研究成果を駆使して敗因を分析し、そこから得た教訓が戦後日本にいかなる影響を与えたのかを探る。
目次
1 勝者の暴走(軍隊と憲法;勝者となって;軍部の政治的台頭)
2 勝者から敗者へ(日中戦争と混迷する戦争指導;戦場と銃後;敗戦)
3 勝者による占領と敗者日本(敗者にとっての戦後;敗者の記憶)
著者等紹介
古川隆久[フルカワタカヒサ]
1962年生まれる。1992年東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。現在、日本大学文理学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nnpusnsn1945
36
太平洋戦争の敗因が明治政府の制度に根源があるとし、近代日本の政治、軍事制度に民意が反映しにくかったとしている。同じ著者の『昭和史』にも同様に書かれているが、本書は講義をベースに作っているため、学術書ではあれど平易な文体である。値段は高いがその分価値は高い。個人の手記に多く言及しているため、当時の状況について想像しやすい。著者は学術会議問題の発言で知られているが、約10年前の本書のまとめを読むと納得がいく。2024/08/15
筑紫の國造
9
明治の建軍からポツダム宣言受諾まで、帝国陸海軍(ほとんどが陸軍)の問題点を探りながら綴った通史。「天皇直属」軍隊がはらむ欠点は、明治の元勲が国民を蔑視した時から始まり、日本の敗戦までついに是正されることがなかった。それでも明治時代はその問題点が表面化することはなかったが、昭和に入ってから組織が官僚化し、軍が「国防」という本来の目的を忘却し、「面子」を重視して結局国を滅ぼすという逆転現象が現出することになってしまった。もともとが著者の大学での講義であることから、文章は平易で読み易い。2017/02/13
マウンテンゴリラ
2
敗者の日本史という、シリーズ本の最終巻であるが、あらためてこの出来事が、長い日本史の中でも最大の悔恨事と言っても過言ではないと感じた。それはもちろん、日本の降伏を指して言うのでは無く、軍国日本に運命を委ねた、その過程も含めた昭和初期以降の歩み全般に対してである。しかも、この未曾有の出来事が、僅か80年と言う、人の一生にも満たない過去の出来事であったと言うのが、感覚的には信じられないほどである。それは、実際に戦中戦後の厳しい生活を経験した人達にとっては、急速な戦後復興の恩恵と言える面もあるだろう。→(2)2022/07/18
MrO
2
まあ、何というか、言葉が出ない。この時代を愚かと笑うことは簡単だが、しかし、少しは賢くなったのかと、昨今のニュースを見ても思うことしばしば。2022/02/18
佐藤丈宗
2
近代日本が勝者(日清・日露戦争の勝利、列強の仲間入り)となり、敗者(第二次世界大戦の敗北)にいたる過程に力点が置かれており、戦後の比重はやや少なめ。紆余曲折を経ながら「近代化」に成功できたかに見えた日本だが、軍部をはじめその体制には大きな歪みを内包していた。いつまでも明治の「成功体験」を克服することが出来ず、歪んだ過去を根拠にして「面子」を大事にした結果、現代日本には一体何が遺されたのか? 過去の「成功体験」にすがり「面子」にこだわる彼らの姿をいまの私たちは他人事のように愚かだと言うことができるだろうか。2017/08/20