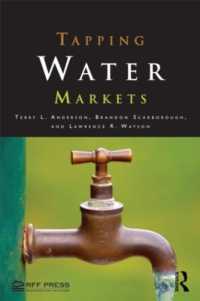出版社内容情報
兄弟の確執?―プロローグ/「越前事」 元和八年の危機(松平忠直の不参事件/本多正純の改易/「大陰謀」の発覚と松平忠直)/確執の始まりと家臣への道(忠長論の展開/国松の誕生と兄弟たち/兄竹千代との世継争い/親藩大名へ)/駿府徳川藩と蜜月時代(家光の将軍襲職と二元体制/駿府徳川藩の成立/駿府徳川藩の展開/母お江与と兄弟の蜜月)/自滅への道(情報を集め、交換する大名/閉塞感ただよう寛永八年/乱行の開始/甲斐甲府への謹慎と赦免の嘆願)/改易そして自害へ(高崎への逼塞と駿府藩の滅亡/忠長の自害とその背景/忠長を語る逸話とその正体)/「代替わり」の危機とその後の忠長―エピローグ
内容説明
三代将軍家光の弟で駿河大納言と呼ばれた徳川忠長。将軍家連枝でありながら、なぜ自害に至ったのか。父母より寵愛を受けた幼少期、駿府藩主時代、改易から自害に至るその全生涯を描き、幕藩政治史のなかに位置づける。
目次
兄弟の確執?―プロローグ
「越前事」―元和八年の危機
確執の始まりと家臣への道
駿府徳川藩と蜜月時代
自滅への道
改易そして自害へ
「代替わり」の危機とその後の忠長―エピローグ
著者等紹介
小池進[コイケススム]
1960年、千葉県に生まれる。2000年、東洋大学大学院文学研究科博士後期課程修了。現在、東洋大学非常勤講師・聖徳大学兼任講師、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
k5
52
江戸力強化月間⑦。どうしても『シグルイ』の暴君を想像してしまう私には、細川忠利の書簡の「御きり候者を明くる日は御よび候」というパワーワードが頭に残ってしまいます。と、いうように、どうしても陰謀論や野次馬的な興味で見てしまう人物ではありますが、大名や金地院崇伝の書簡などの一次資料を駆使した臨場感のある良い本だと思います。2022/05/21
ようはん
23
序盤で取り上げられている越前松平家の松平忠直蟄居事件やそれより前の松平忠輝改易事件を考えると大坂の陣後における幕府の最大の脅威は有力な外様大名よりも反幕府の旗頭になり得て将軍位も狙える大封の親藩大名の方であると感じる。家光とそこまで関係が悪い訳ではなかった忠長が乱行に走り自滅したのは幼少の頃と比べた兄家光との扱いの差や英邁な異母弟である正之の出現による危機感等が挙げられているが、自身と同じく大封を持ちながら潰された忠輝・忠直という一門の存在がいたのもプレッシャーを与えていたのだろうかと思った。2021/07/29
さとうしん
19
家光と忠長の関係は巷間に言われてるほど悪いものではなく、むしろ良好だったと見られるが、忠長の乱行は幼少期に両親に偏愛されたこととその後の状況とのギャップ、そして異母弟正之の出現が影響しているのではないかとのこと。家光は最後まで弟の改悛を望んでいたが、秀忠死後の政治状況の不安定さもあり、悲劇的な結末となったとする。忠長像というより家光像をやや塗り替えたという印象を受けた。2021/07/20
MUNEKAZ
15
徳川忠長の評伝。よく言われる兄・家光との確執は否定し、むしろ兄弟仲が悪くなかった部分を、史料に基づき論証している。父母の溺愛よる自身への過信など、著者なりに乱行の理由も挙げているが、やはりすっきりはしない。小説ではないので、結局のところ「気狂い」になったとしか言えないのが限界か。また父・秀忠が、あっさりと忠長を見放すのも意外で、弟や甥を容赦なく改易した果断さが見て取れる。家光にとっても舐めた態度をとる弟を切れるかは、年長の御三家や家門大名に、徳川家の家長として示しをつける意味で、試練だったのであろう。2023/11/18
katashin86
7
家光の「出来の良い弟」駿河大納言忠長の短い人生からみる江戸時代初期・幕藩体制確立期。外様大大名と同世代人であった家康・秀忠と異なる「生まれながらの将軍」三代家光こそ、有力親藩・徳川一族中で比較しての正当性・安定した基盤を欠く存在であり、ゆえに乱行を重ねる弟の存在を体制として許容できなかったという視点がとても興味深かった。ある時期まで忠長を甘やかす父秀忠が、忠長をバッサリと見切る瞬間の恐ろしいこと。2021/12/18