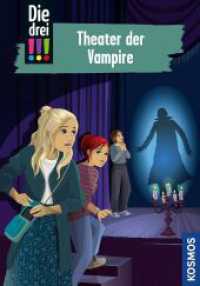出版社内容情報
7?10世紀、中国東北部から朝鮮半島北部にかけて栄えた渤海国。この歴史は長く忘れられていたが、こんにち、周辺各国が自国とのかかわりのみを強調しがちな「歴史の争奪」が起きている。こうした対立を乗り超えるため、国際交流を軸に、地域の大きな枠組みに焦点を合わせて多元的に捉え直す。河川流域に拠点を築いた多種族国家の実像に迫る。
内容説明
古代の中国東北部~朝鮮半島北部に栄えた渤海国。この国の歴史を、現在各国が自国とのかかわりを強調して描きだしがちである。その対立を乗り越えるため、国際交流を軸に、地域の大きな枠組みに焦点を合わせ捉え直す。
目次
渤海国の「再発見」―プロローグ
渤海史概説(渤海国の基本史料と基本データ;建国から「海東の盛国」へ;「海東の盛国」から滅亡へ、そして遺民たち)
ユーラシアのなかの渤海国(東アジア世界のなかの渤海国;東部ユーラシア世界のなかの渤海国)
東北アジアのなかの渤海国(東北アジアという地域;古代東夷の世界とその南北分割;満洲世界の成立)
海洋国家としての渤海国(環日本海世界のなかの渤海国;環黄海・東シナ海世界のなかの渤海国)
「歴史の争奪」を超えて―エピローグ
著者等紹介
古畑徹[フルハタトオル]
1958年東京都に生まれる。1981年東北大学文学部史学科卒業。1987年東北大学大学院博士課程後期単位取得退学。金沢大学人間社会研究域歴史言語文化学系教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- BLINK×BLINK3 アイプロセレ…