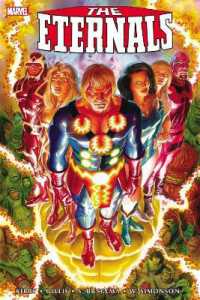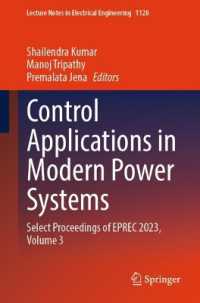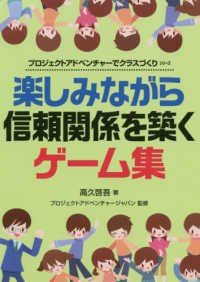内容説明
私たちを取り巻くすべてのモノが持つ「名前」は、どのように命名されてきたか。観察・解釈して表現した「名づけ」的命名と、未来への期待や決意を示した「名のり」的命名に分類してその実態を分析。今後の命名を考える。
目次
モノの名前―プロローグ
物に名をつけること
生活から地名が生まれる
地域名の展開
家の名、人の名
さまざまな命名
現代の命名事情―エピローグ
著者等紹介
田中宣一[タナカセンイチ]
1939年、福井市に生まれる。1967年、國学院大學大学院文学研究科博士課程単位取得退学。現在、成城大学名誉教授、博士(民俗学、國學院大學)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
20
地名・人名から魚の名、大学名まで、日本の「名前」の付けられ方共通のしくみをさぐろうとする一冊。自分はこれまで、合併や住居表示の変更などのたび旧来の地名が捨てられるのを苦々しく思い、一方で合成地名やイメージ地名は×だと感じてきたし、その感覚を疑いはしなかったが、田中はもう一段引いた視点から、それもまた名づけだ、という。確かに同じ合成地名でも鉄道の路線名には抵抗はないし、親の名づけは「こうあってほしい」という願望そのもの、新地名とは程度の差しかない。結局、どちらで当事者が納得できるか、対話しだいということか。2014/04/22
びっぐすとん
17
図書館本。『日本人の姓・名前・苗字』と重なる部分もあるが、こちらでは地名や物の名前も検証。震災の時に言われていたが古い地名や字には過去の災害の手掛かりもあるので、地域で伝えていくことが大事だと思った。よく遺跡でみかける「○○作」も誰かが開墾した新田という意味かな?母方の親戚に「アライのおじさん」という人がいて「新井さん」だと思ったら、「アライ」は分家のことと母に言われたのを思い出した。「新たに居を構えた」ということだったのかな?忌み言葉も興味深いし、小○製薬のような商品名に関する話ももっと知りたかった。2019/12/02
Riju
4
名付けに関して人名だけでなく、地名、川、山など別の視点から広く捉えている印象。現代というよりは昔からの命名における変遷についてという感じ。また、最後に現代の名付け事情にも触れているがおまけ程度。あらゆるものへの名付けの歴史書っぽい。2014/11/21
ダージリン
3
姓、氏、苗字の違いなどは面白かった。明治になって全員が苗字を持つことになったとは知っていたが、武家以外が苗字を持つことが禁じられたのは江戸時代で苗字がない時期がさほど長くはなかったことは知らなかった。山、川、地名、生物など、名前について幅広くトピックスがあり楽しめた。2025/01/07
yurari
3
著者のように様々なモノの名前をまとめる人がいないと、忘れ去られてしまうものも多いのだろうなぁ。/命名とは、あるモノを他のモノと区別するために、短い的確な言葉で説明しようとする行為。対象物を人々がいかに認識しているかの言語的表現。逆に言えば、モノの名から人々のモノへの認識の仕方や、万物との関わりを知ることができる/名前に関心を示さないのは、そのモノを認識しなくても構わない生き方、そういう文化だから。微妙な風に反応する漁師や船乗りとそうでない人々との違いは、風という現象に対する自然観の相違/2023/02/19