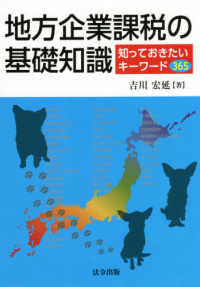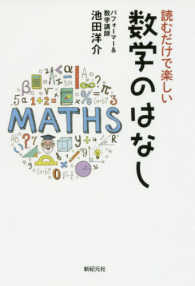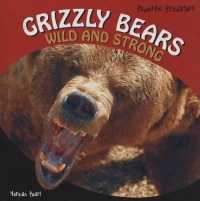内容説明
日本古代史を知る第一の古典『日本書紀』を“史料”としてではなく“書物”として読み解く新たな試み。『日本書紀』が朝鮮古代史の宝庫でもある理由を探り、古代国家日本の成立を記した、ひとつの「歴史書」誕生の物語。
目次
書物としての『日本書紀』―プロローグ
天皇の年代記
東アジアの動向と『日本書紀』
百済史書と書記官たち
百済史書と『日本書紀』
誕生した歴史書―エピローグ
著者等紹介
遠藤慶太[エンドウケイタ]
1974年、兵庫県に生まれる。1997年、皇學館大学文学部国史学科卒業。2004年、大阪市立大学文学研究科博士後期課程修了。現在、皇學館大学史料編纂所准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はちめ
14
日本書紀を読んで驚かされるのは朝鮮半島との関係や、朝鮮半島自体に関する記述が多いことだ。日本書紀を編集した人たちの意図は何だったのか、そもそも朝鮮半島の国々、特に百済と倭の関係はいかなるものであったのか大いなる謎だと言える。本書は、百済側の歴史書であったと推測される百済記などと日本書紀の関係を説明しようとするものである。著者の古代史感についていけないところもあるが、興味深いアプローチなので後日再読したいと思う。☆☆☆☆2020/09/08
hyena_no_papa
10
他の方の感想が余りにも適切なので私が特に採り上げることはなさそう。『日本書紀』という「歴史書の誕生」について要点別に解説。百済三書との関連は漠然とは読み知っていたが、著者の考察に触れて一歩理解が進んだかも知れない。百済の滅亡に伴う亡命百済人たちが大王家や朝廷に深く関わっていることが再認識される。『三五暦記』から「甲寅」「天皇」について説く箇所には大きく頷く。ともあれ『日本書紀』は素人が軽々に云々できるものではないことを改めて自覚。ただ、本書をもってしても大和朝廷の創始については依然闇の中を彷徨う如し。2021/10/31
はちめ
7
日本書紀の編集に百済からの渡来人と百済紀などの史書が関係しているのは確かだろうが、日本人の関わりはどうだったんだろうか。日本書紀の原稿を書くのは百済系の技術者だとしても、それをチェックする日本側の官僚はいたのではないか。そのような中で、日本側を貴国と表記しているおかしさをチェックできなかったのはどうしてだろうか。日本側官僚には漢文のチェック能力が欠けていたのだろうか。また対外関係としては百済だけではなく新羅や高句麗との関係も記されているが、これらの情報はどのようにもたらされたのか。続編が欲しい。☆☆☆☆☆2022/08/21
坂津
6
東アジア、その中でも主に百済との関係性に着目することで、七世紀以前の歴史記録がどのようにして『日本書紀』として集成されたのか考察した書籍。辛酉革命説(神武天皇の即位を推古天皇九年(601年)から1260年遡らせて設定したとする説)、四・五世紀の外交記事における紀年のずれ(干支二運(120年)分遡らせた紀年設定)、分註として引用される百済史書(「百済記」「百済新撰」「百済本紀」)の成立過程とその影響など、東アジアの歴史の中で『日本書紀』を位置付ける際に把握しておきたい事項が余すことなく取り上げられている。2021/02/12
パパ
6
日本書紀は編纂書であり、様々な原典がある。また、勅撰書で編者として親王が名を連ねているが、実際に編纂した人間もいる。この謎に挑んだのが本書である。 戦後の日本史では、継体崩御後の皇位継承問題、仏教伝来の年代問題など、テキストとしての日本書紀が、政治的意図に基づいて書き換えられたとして軽視されるが、本書では明解な根拠をもって日本書紀の内容を事実としている。 日本書紀の編纂に実際に携わったのは百済の史官で、百済滅亡前後に渡来してきた人間とし、烏羽の表の王辰爾の兄弟の後裔(葛井氏、船氏、津氏)と推測している。2012/09/09