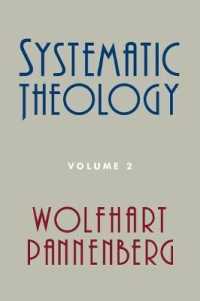出版社内容情報
★読売新聞 2009.6.28 に紹介されました! 評者:本郷和人氏(日本中世史家)
内容説明
室町幕府成立後の尊氏・直義兄弟の確執は、義詮・直冬の争闘を経て、幕府と鎌倉府という二つの支配体制成立の要因となる。対立の実態を『太平記』などから当時の政治過程に位置づけて再現。神護寺三画像の比定も試みる。
目次
歴史における兄弟の相剋―プロローグ
足利氏のふるさと―足利荘と鎌倉
室町幕府成立へ―尊氏・直義のあゆみ
室町幕府と観応の擾乱
「薩〓(た)山体制」の成立と崩壊
尊氏・直義の人物像
京の夢、鎌倉の夢―エピローグ
著者等紹介
峰岸純夫[ミネギシスミオ]
1932年群馬県に生まれる。1961年慶応義塾大学大学院文学研究科修士課程修了。現在、東京都立大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あきあかね
26
「豆を煮るに豆がらをたく」―兄弟が傷つけ合うことのたとえ(広辞苑) 1991年のNHK大河ドラマ『太平記』では、足利尊氏が弟直義に毒を盛る場面が鮮烈だった。鎌倉幕府の打倒、南朝との対立にあたり、ともに力を合わせてきた兄弟であったが、1350年に起こった観応の擾乱で、両者は対決する。敗れた直義は尊氏と和議を結ぶがまもなく没する。ドラマでは、尊氏が勧める菓子に毒が入っていることを知りつつもそれを口に運ぶ直義と、毒に悶え苦しむ直義の声をかき消すかように幼い日の思い出を滔々と語る尊氏の姿が心に刻まれた。⇒2020/03/05
叛逆のくりぃむ
7
正妻である金沢貞顯妹について觸れなかつたりと史料的には舊さがある。2015/12/14
nob
5
『観応の擾乱』の参考書として。 軍事尊氏・政務直義の担当二分体制(『観応の擾乱』では否定されてた)から、薩埵山体制を経て、京・鎌倉府という地域二分体制が確立する過程が本書の軸。さらに残された資料をもとに兄弟の人間性にも迫る。 感傷的なサブタイトルの割には読みやすい本ではないが参考になる。2018/11/28
ダージリン
4
足利尊氏と直義の対立についてはあまり詳しく知らず、どのような闘争があったのかを知りたくて手にしてみた。義詮、直冬、高師直などを含めた確執が生み出した展開を見て、わずかながらこの対立関係を理解できた気がする。京都の幕府と鎌倉府の支配体制の成立についても理解が深まった。2025/04/08
いきもの
3
鎌倉幕府崩壊から、足利尊氏と直義の兄弟政権体制、その後の対立が深まる構図、尊氏、直義の死後実現される京と鎌倉の兄弟国家実現。足利兄弟の周辺を丁寧に書いてはいるものの、著者の研究をまとめていると見受けられる部分も多くやや軸がぶれている。直義の夢であった鎌倉府というのもよくわからない。特段意外性のある内容などはないが無難にまとまっている気はする。2014/05/16