内容説明
明治時代の半ばから、日本人の主食=米は不足し始めた。凶作による米価暴騰、輸入米の増加、残飯屋の繁盛、流通の変化、産米改良の動向、節米生活下の家計を辿る。米不足との闘いが、「米過剰」の現代に伝えるものを考える。
目次
日本人と米食―プロローグ(米不足の時代;米食の拡大 ほか)
米不足の時代へ(連年豊作;米価暴騰と米穀輸入)
米食のひろがり(都市の米食;農村の主食 ほか)
産米改良と産地間競争(北陸・東北の産米改良;西日本の防長米・肥後米の改良 ほか)
拡大する米消費―米騒動前後(米価の騰落と消費;難航する外米輸入 ほか)
著者等紹介
大豆生田稔[オオマメウダミノル]
1954年、東京都に生まれる。1978年、東京大学文学部国史学科卒業。東洋大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イボンヌ
3
日本には美味い米がある。それは先人達のたゆまぬ努力と改良によるものです。 日本には米がある。2020/01/12
たまな
2
米食は日本の伝統食と思われていますが、昭和初期の時期でも、雑穀や芋などが多く取り入れられていたこと。年貢のしくみがなくなったことで、米の品質が著しく低下したこと。明治時代の都市の貧民は軍や学校から出る残飯を買っていたことなど、知らなかったことがたくさんありました。 たった百年ほどで、日本の食は大きく変わっています。おいしいお米が食べられるのが普通になったのは、ごく最近のことなのですね。 01/22 13:222016/01/10
コカブ
2
明治~戦前期にかけての、日本の米についての本。こういう視点で歴史を考えた事がなかったので、目新しさが良かった。明治維新後は米価が上昇して農村が潤ったが、松方デフレで米価が下落した。1890年頃から再び米価は上昇する。国内米の不足を補うために、外米の輸入が行われるようになった。所得の上昇で都市には米食が普及し、農村でも次第に米食の割合が高まっていった。国内米の不足は外米で補われたが、1918年には外米の輸入が困難になって米が高騰し、米騒動が起こった。2012/10/25
双海(ふたみ)
1
ゼミで参考にしました。2013/08/05
-
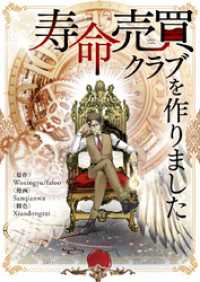
- 電子書籍
- 寿命売買クラブを作りました【タテヨミ】…








