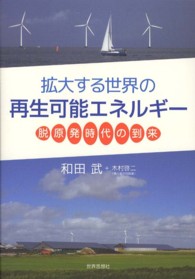内容説明
近世の江戸で、最高の消火技術と独特の文化を誇った町火消、その技と気概は維新以後も生き続けた。だが、近代建築の登場と技術発展のなか、次第に消防の主役も変化していく。本書は、消防の近代化のなかから伝統と革新を考える。
目次
江戸の火消
幕末・維新期の町火消
警視庁による消防再編
「近代的」消防体制の確立
近代水道と消防組
消防自動車の時代
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
びっぐすとん
12
図書館本。『ぼろ鳶組』の影響で読んでみた。江戸時代の火消しに関する内容は少なめだった。源吾たちの時代より後になると定火消は衰退し、町火消が主流になっていく。明治以降は宙ぶらりんな状況が続き、やがて官製の消防士へと移行していくが、待遇が悪かったり、警察の派生業務みたいだったりと、なかなか専門職として確立してないが、建物の西洋化、耐火性が進むと江戸時代の火消しでは対応出来なくなっていく。水道の整備と蒸気ポンプ車が消防の近代化を前進させた。西洋が戦争、ペスト、コレラに襲われた時代、日本の最大の災害は火災だった。2020/01/23
印度 洋一郎
1
「暴れん坊将軍」でも知られる、江戸の消防を担った町火消。彼らが幕末・維新を経て、どうなったのか? 意外に知られていない日本消防史の一面を探る。プロの消防組織を作ろうとした新政府の政策はなかなか上手くいかず(財政上の問題で)、明治になっても町火消達は「消防組」と改組され、東京の消防を担っていたようだ。しかし、消防ポンプや消防車といったテクノロジーの導入によって、教育を受けた消防士が必要とされ、明治から大正にかけて、徐々に消えていく。しかし、その伝統は東京消防庁へと吸収され、正月の出初式に名残を残している。2012/02/22