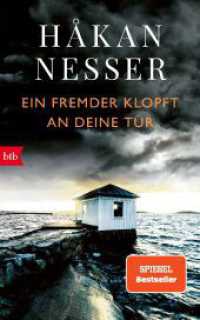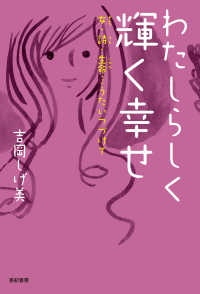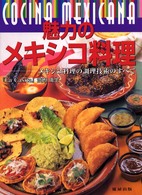内容説明
悪党は武装して歴史に登場した。派手な甲胄、光りきらめく太刀・長刀のいでたちは、綾羅錦繍に通じる反逆の表象でもあった。ゲリラ戦の楠木正成、バサラの佐々木道誉らをまじえ、内乱を生きた人間の意識と行動にせまる。
目次
悪党の出現
大仏を領主にする村
悪党の活動
武装の行粧
内乱の風景
悪党の美学
悪党の終焉
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こぽぞう☆
14
図書館本。「悪党重源」からの流れで借りたが、かなりあとの時代の話だった。大寺社の荘園における民衆がいわゆる「悪僧」の部分、それもかなり大きな部分となっていたこと。そこから甲冑を帯びるものとなり、寺社から独立し南北朝の動乱期へと入っていく。芸能や婆娑羅大名も関連して出てくる。2019/05/13
やまだてつひと
4
最初は荘園内の武力衝突がどんどん広がりいく様や、行動の規範になる教えが形骸化し、経済的な価値のみを信じるようになった結果。治安が荒れていく様というのは、昔からあったのだと再認識させられた。あとがきの部分にはなるが「イデオロギー的意味を押し付けるのではなく、イデオロギー的な意味を破壊することによって、みずからを維持している」(テリー・イーグルトン 『イデオロギーとは何か』平凡社)の言葉が非常に印象に残った2024/05/19
浅香山三郎
3
多くの悪党研究で知られる新井氏による一般向けの本。黒田荘の悪党をまず詳しく紹介し、荘園制的支配の強化に対する抵抗勢力として悪党を捉へる。楠木合戦におけるゲリラ戦や、南北朝内乱における傭兵的な武力の実態、さらにはバサラ大名の価値観など、「悪党の世紀」の精神を広く紹介する。著者が言及する海津一朗氏の研究を始め、その後の研究の進展も追ひかけてみたい。13世紀末の鎌倉幕府(得宗専制)や京都の公家政権の分立など、政治史の動きも組み込むと、網野善彦さんの『蒙古襲来』のやうに理解の幅が広がりさうに思へた。2016/02/11
邑尾端子
3
鎌倉末から南北朝までの動乱期に跳梁した、楠正成などの「悪党」や、高師直・土岐頼遠・佐々木導誉などの「バサラ者」について、その発生・消失過程と背後の時代観や文化について。「悪党」が消失する過程は、それまで悪とされた「武」の要素がごく一般的なものとして社会全体を覆ったからという説明ですっきり理解できるのだが、発生の過程はいまいち理解しきれない部分があった。荘園体制の崩壊が「悪党」発生の要因であるとされるが、逆に「悪党」の発生により荘園体制が崩壊したようにも見える。もちろん相互作用はあるだろうけども・・・2013/11/22
しんさん
1
中世日本のアウトロー。はみだしちゃった人たちの、時代と意識。2014/12/16
-
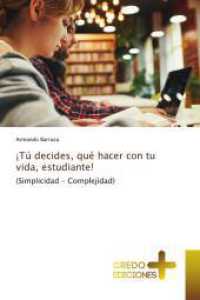
- 洋書
- ¡Tú de…