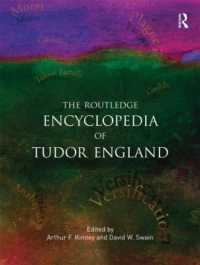出版社内容情報
『日本霊異記』などの史料論的考察をおこない、地方の仏教施設での説法の様子や階層性を分析。仏教受容のあり方と特質を解明する。『日本霊異記』『東大寺諷誦文稿』の史料論的考察を基礎とし、中国史料からの影響を踏まえたうえで、地方の「寺」や「堂」と称される仏教施設での説法の様子や階層性を分析。国家仏教を担っていた僧が在地に関与する一方、在地の支配者層は積極的に支配手段として仏教を受容していたことを明らかにし、日本古代の在地社会における仏教の特質に迫る。
序章 日本古代仏教史像の再検討/日本古代仏教史料論(『日本霊異記』と中国仏教説話―化牛説話を中心に〈古代中国の畜類償債譚の展開/『日本霊異記』の史料性と化牛説話の位置/『日本霊異記』の化牛説話と在地の仏教〉以下細目略/『東大寺諷誦文稿』の史的位置/御毛寺知識経と在地社会)/日本古代在地仏教論(『日本霊異記』の仏教施設と在地の仏教/『日本霊異記』の仏教施設の造営主体―「堂」を中心として/『東大寺諷誦文稿』の「堂」と在地の仏教―「慰誘言」を中心として/在地社会の法会の特質―僧侶を中心として)/附論 古代村落の「堂」と仏教統制―山城国愛宕郡賀茂郷の「岡本堂」をめぐって/終章 総括―古代国家仏教と在地社会
藤本 誠[フジモト マコト]
内容説明
『日本霊異記』『東大寺諷誦文稿』の史料論的考察を基礎とし、中国史料からの影響を踏まえたうえで、地方の「寺」や「堂」と称される仏教施設での説法の様子や階層性を分析。国家仏教を担っていた僧が在地に関与する一方、在地の支配者層は積極的に支配手段として仏教を受容していたことを明らかにし、日本古代の在地社会における仏教の特質に迫る。
目次
日本古代仏教史像の再検討
第1部 日本古代仏教史料論(『日本霊異記』と中国仏教説話―化牛説話を素材として;『東大寺諷誦文稿』の史的位置;御毛寺知識経と在地社会)
第2部 日本古代在地仏教論(『日本霊異記』の仏教施設と在地の仏教;『日本霊異記』の仏教施設の造営主体―「堂」を中心として;『東大寺諷誦文稿』の「堂」と在地の仏教―「慰誘言」を中心として;在地社会の法会の特質―僧侶を中心として;古代村落の「堂」と仏教統制―山城国愛宕郡賀茂郷の「岡本堂」をめぐって)
総括―古代国家仏教と在地社会
著者等紹介
藤本誠[フジモトマコト]
1976年神奈川県に生まれる。2002年慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程史学専攻日本史分野修了。現在慶應義塾大学文学部助教・博士(史学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。