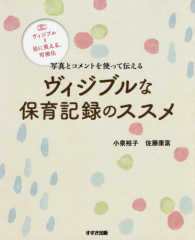出版社内容情報
古代日本の地方を領域支配するための行政機構=国・郡・里制とはいかなるものだったのか。木簡や漆紙文書、墨書土器など、文字資料を駆使し古代社会を解き明かしてきた著者による研究書下巻。里と村、郡・村印と私印、国・郡・里およ
内容説明
古代日本の地方を領域支配するための行政機構=国・郡・里制とはいかなるものだったのか。木簡や漆紙文書、墨書土器など、文字資料を駆使し古代社会を解き明かしてきた著者による研究書下巻。里と村、郡・村印と私印、国・郡・里および村を結ぶもの―駅家と駅制、海・河川、馬について、地名表記の墨書・刻書土器・出土古印と印影などから実像に迫る。
目次
第5章 里と村(「里長」と「里刀自」;古代における里と村)
第6章 郡・村印と私印(古代郡印論;郡「佐」銅印―秋田県由利本荘市川口の大覚遺跡出土銅印;長野県内出土・伝世の古代印の再検討;発掘された村の印―「磐前村印」)
第7章 国・郡・里および村を結ぶもの1―駅家と駅制(蚶形駅家―秋田県秋田市秋田城跡出土第一〇号漆紙文書;山陰道粟鹿駅家―兵庫県朝来市柴遺跡出土木簡;東海道推定安候駅家跡(東平遺跡)出土の「騎兵長」墨書土器
甲斐国駅制再考
烽遺跡発見の意義)
第8章 国・郡・里および村を結ぶもの2―海・河川(古代における地域支配と河川;古代港湾都市論―犀川河口と河北潟沿岸遺跡群出土文字資料から;港湾と海上ルート―中世都市鎌倉以前)
第9章 国・郡・里および村を結ぶもの3―馬(古代社会と馬―東国国府と栗原郷、「馬道」集団)
著者等紹介
平川南[ヒラカワミナミ]
1943年山梨県に生まれる。1965年山梨大学学芸学部卒業。1990年文学博士(東京大学)。2006~14年国立歴史民俗博物館館長。現在、人間文化研究機構理事・国立歴史民俗博物館名誉教授・山梨県立博物館館長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 杖道