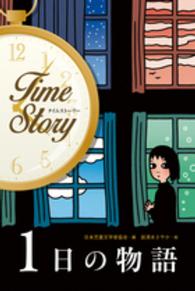内容説明
江戸時代の林野には、どのような樹木がどれくらい茂っていたのか。また、そこにはどのような動物が生息し、林野や野生生物の様相と、地域の人々の暮らしのあり方には、どのような関わりがあったのか。広島藩領を中心に林野の利用や、シシ(猪鹿)垣・たたら製鉄などを分析。瀬戸内の島々から沿岸部、さらに内陸部についての自然と人々の暮らしを解明。
目次
近世(江戸時代)の暮らしと自然を考える
1 人々の暮らしと林野(広島藩沿海地域における林野利用とその「植生」;沿海地域の林野利用―賀茂郡三津村・豊田郡生口島の事例から;山間地域の林野利用―たたら製鉄と備後炭の出雲・伯耆流通)
2 人々の暮らしと野生動物(近世広島の猪と豚;安芸のシシ垣;石見銀山領における猪被害とたたら製鉄)
3 経済活動の活発化と人々の暮らし(瀬戸内中部の港町と流通;広島藩沿海地域の人口増加と島嶼村落)
著者等紹介
佐竹昭[サタケアキラ]
1954年和歌山県に生まれる。1979年広島大学大学院文学研究科博士課程後期中途退学。現在、広島大学大学院総合科学研究科教授、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 和書
- 前立腺癌診療マニュアル