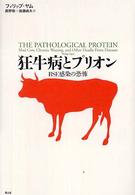出版社内容情報
山村の人々はなぜ山を下りず住み続けたのか。生活文化体系の視座に立って山村の生業や特質、外部社会との交流などを解き明かす。現代よりはるかに不便であったはずの近代以前、山村の人々はなぜ山を下りずに住み続けたのか。信濃国秋山と甲斐国早川入を中心に、生活文化体系の巨視的な視座から中近世山村の生業や特質、外部社会との交流などを解明。自然環境の多様な利用方法、近隣との山野争論、野生動物の狩猟などの事例から、従来の山村=「後れた農村」観に一石を投じる。
序章 山村と歴史学―生活文化体系という視座から/山村の生業と生活文化体系(近世山間地域における環境利用と村落―信濃国秋山の生活世界から〈秋山の生業と生活/「生活文化体系」の視点から/根幹的志向としての「自律」〉以下細目略/近世山村の変貌と森林保全をめぐる葛藤―信濃国秋山の自然はなぜ守られたか/山地の資源とその掌握/山村と飢饉―信濃国箕作村秋山地区の事例を通して)/山という場の特質(山の世界と山野相論―紀伊国名手・粉河相論を手がかりに/野生と中世社会―動物をめぐる場の社会的関係)/外部世界との交流(中世山間庄園の生業と外部交流―若狭国名田庄/近世山村のネットワーク―甲斐国早川入と外部世界の交流)/終章 前近代日本列島の資源利用をめぐる社会的葛藤
白水 智[シロウズ サトシ]
著・文・その他
内容説明
現代よりはるかに不便であったはずの近代以前、山村の人々はなぜ山を下りずに住み続けたのか。信濃国秋山と甲斐国早川入を中心に、生活文化体系の巨視的な視座から中近世山村の生業や特質、外部社会との交流などを解明。自然環境の多様な利用方法、近隣との山野争論、野生動物の狩猟などの事例から、従来の山村=「後れた農村」観に一石を投じる。
目次
山村と歴史学―生活文化体系という視座から
第1部 山村の生業と生活文化体系(近世山間地域における環境利用と村落―信濃国秋山の生活世界から;近世山村の変貌と森林保全をめぐる葛藤―信濃国秋山の自然はなぜ守られたか;山地の資源とその掌握;山村と飢饉―信濃国箕作村秋山地区の事例を通して)
第2部 山という場の特質(山の世界と山野相論―紀伊国名手・粉河相論を手がかりに;野生と中世社会―動物をめぐる場の社会的関係)
第3部 外部世界との交流(中世山間庄園の生業と外部交流―若狭国名田庄;近世山村のネットワーク―甲斐国早川入と外部世界の交流)
前近代日本列島の資源利用をめぐる社会的葛藤
著者等紹介
白水智[シロウズサトシ]
1960年、神奈川県に生まれる。1983年、上智大学文学部卒業。1992年、中央大学大学院文学研究科単位取得満期退学。現在、中央学院大学法学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
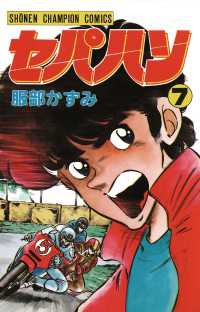
- 電子書籍
- セパハン 7 少年チャンピオン・コミッ…