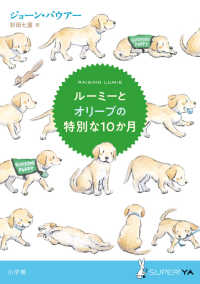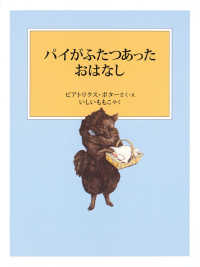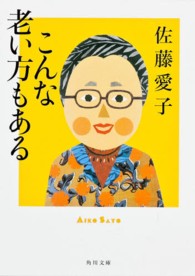出版社内容情報
日本古代の女性は地域社会のなかでどのように生きたのか。〝家族〟を超えた社会的な役割を、村レベルでの女性の経営機能と国家によるその掌握を通して探る。さらに、王権祭祀における女性祭祀者の意義を考察し、〝女=聖〟という霊的優位性の観念を批判的に再検討。生活・祭祀・家族を総合する視点から、古代女性の実像を解き明かす。
内容説明
日本古代の女性は地域社会のなかでどのように生きたのか。“家族”を超えた社会的な役割と“女=聖”という霊的優位性の観念を批判的に再検討。生活・祭祀・家族を総合する視点から、古代女性の実像を解き明かす。
目次
古代女性史研究の転換点にたって
1 生活と経営(古代の村の生活と女性;「刀自」考―首・刀自から家長・家室へ;「田夫」「百姓」と里刀自―加賀郡〓(ぼう)示札における魚酒型労働の理解をめぐって ほか)
2 祭祀の編成(刀自神考―生産・祭祀・女性;御巫の再検討―庶女任用規定をめぐって;「女巫」と御巫・宮人―鎮魂儀礼をめぐって ほか)
3 家族・親族・氏族(古代の家族と女性;婚姻と氏族;イヘの重層性と“家族”―万葉歌にみる帰属感・親愛感をめぐって ほか)
著者等紹介
義江明子[ヨシエアキコ]
1948年大阪に生まれる。1971年東京教育大学文学部史学科卒業。1979年東京都立大学大学院人文科学研究科修士課程修了。帝京大学文学部教授、文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
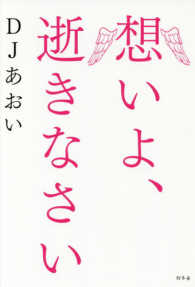
- 和書
- 想いよ、逝きなさい