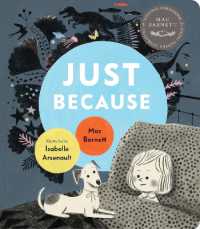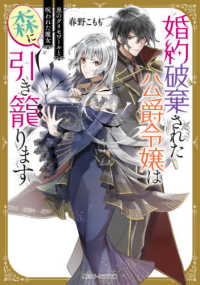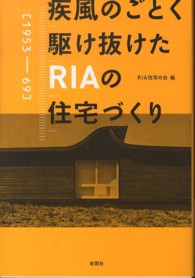内容説明
ある概念ある思想が、世間に普及し陳腐化したように思われた時に、私たちは逆にその思想を洗い直し、誕生の時点にまでさかのぼって見つめ直す必要がないでしょうか。そのような検討に耐える思想が真に“古典”と呼ばれるにふさわしいものです。ロジャーズの“クライエント中心”という考え方は、まさにこの古典に当たります。本書は、彼の生涯と思想・実践の体系の中に、その核心を位置づけ、ロジャーズ自身を浮き彫りにしました。
目次
第1章 ロジャーズの生涯と思想
第2章 非指示的療法
第3章 クライエント中心療法
第4章 ロジャーズのパーソナリティ理論
第5章 クライエント中心療法の研究
第6章 エンカウンター・グループとPCA
第7章 クライエント中心療法の理論的・実践的な展開
第8章 クライエント中心療法近縁の心理療法
著者等紹介
佐治守夫[サジモリオ]
1924年山形市に生まれる。1948年東京大学文学部心理学科卒業。1996年逝去。専攻は臨床心理学・教育心理学。元東京大学名誉教授
飯長喜一郎[イイナガキイチロウ]
1945年上越市に生まれる。1969年東京大学教育学部教育心理学科卒業。専攻は臨床心理学。現在、日本女子大学人間社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kayak-gohan
37
日本におけるカウンセリングは「傾聴」をその基礎に置く。これはカール・ロジャーズの理論に準拠し、「パーソナリティ変化の必要にして十分な条件」が満たされることでカウンセリングが進行するという考え方である。本書では、彼の理論が如何にして誕生し、成立へ至ったかの過程がわかりやすく説明されている。さらに、パーソン・センタード・アプローチへの理論発展やエンカウンター・グループという手法にも触れられている。入門書といった趣だが、自分にはいまだ難解なところも多い。今後カウンセラーとして面談経験を積んでから再読してみたい。2016/02/21
紫羊
23
ロジャーズの生涯と思想、非指示的療養、クライエント中心療養、パーソナリティ理論、エンカウンター・グループとパーソン・センタード・アプローチ等について、7人の執筆者が概要を紹介しています。さらに詳しく書かれた本を読んでみたくなりました。2015/03/20
ルート
22
カウンセラーとして関わるときのために、第3章の「治療上のパーソナリティ変化の必要にして十分な六つの条件」を再学習した(無条件の肯定的関心、感情移入的理解など)。勉強を教える学習支援者の立場としては、第7章の「教師としての姿勢」の7つの質問文が参考になる(批判しない。自分自身でいる。認める。好奇心の援助、受容などに関する)。質問のほとんどに「奇跡的に」「イエス」と答えられるならば、若い人びとの大きな可能性を引き出すお手伝いができるだろう、とのこと。時々確認したいなぁ。2018/12/17
ハイポ
18
■以下の六条件が長期間継続することで、クライエントに建設的なパーソナリティ変化が起こる。①前提:二者が心理的な接触をもつ②クライエントの条件:不一致の状態(自己像と現実の乖離)にある③セラピストの条件1:一致、統合されている④セラピストの条件2:無条件の肯定的感心(相手が体験している全てに感心を持ち受容する)⑤セラピストの条件3:感情移入的な理解(相手の私的情緒的世界をあたかも自分自身のものであるかのように感じとるが、没入しない)⑥双方の条件:感情移入的理解と無条件の肯定的感心がクライエントに伝達される2022/08/04
みき
10
ロジャーズがブーバーやキルケゴールに影響受けてたと知って、わーと感動した。自分が好き、と思った心理学とか哲学とか、全て体系的に同じところから発展してるのが最近わかってきて嬉しい。分裂的だと思ってた自分に芯が見えた感じ。 もしかしたら、理性もイデアも存在しちゃう? とテンション上がる。2021/03/06
-

- 電子書籍
- 2020年人工知能時代 僕たちの幸せな…