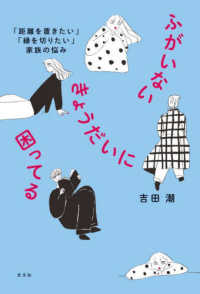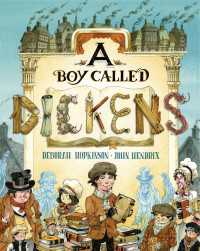内容説明
一九五〇年代後半、ソ連の軍事・科学技術と経済成長が西側諸国に衝撃を与え、フルシチョフ・ソ連共産党第一書記は、ソヴィエト社会主義体制がアメリカ資本主義体制を凌駕すると豪語していた。財政赤字の解消を至上課題とし、長期的に冷戦を戦おうとする米アイゼンハワー政権は、通常兵力の縮減と核戦力への依存による大量報復戦略をとった。しかし、国際的に守勢に回ったかに見えるアメリカが問われていたのは、アメリカの体制、生活様式そのものなのであった。著者は、アイゼンハワー政権の対ソ封じ込め政策が、スターリン死去後のソ連の脅威の性格の変化や冷戦の変容に対応し、軍事的な封じ込めのみに傾斜することなく、経済、文化、広報など広範な手段を取り入れたものであったことを指摘する。アイゼンハワー政権の東西交流計画は、ソ連との軍拡競争の激化を避けて国際的な緊張緩和を辛抱強く進め、人的・文化的交流の拡大・深化を通じてソヴィエト体制の長期的変容を促す、新たな封じ込めの手段であった。
目次
第1章 アイゼンハワー政権の安全保障政策の基本方針
第2章 冷戦の変容と封じ込め手段の多様化
第3章 スプートニク、ゲイサー報告書とミサイル・ギャップ論争の始まり
第4章 「全面的な冷戦」
第5章 東西交流の拡大と深化
第6章 ミサイル・ギャップ論争の進展と東西交流
著者等紹介
佐々木卓也[ササキタクヤ]
1958年、北海道に生まれる。1981年、一橋大学法学部卒業。1985‐87年、オハイオ大学大学院留学。1988年、一橋大学大学院法学研究科博士課程単位修得。関東学院大学法学部専任講師、同助教授、立教大学法学部助教授、イェール大学客員研究員(1997‐99年)などを経て、立教大学法学部教授(アメリカ外交史専攻)、博士(法学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。