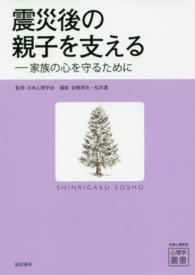内容説明
日本人はどのように塩作りと、関わってきたのか。製塩のための設備や用具、製塩技法、塩にまつわる言葉の数々。さらには製塩業の経営や塩の流通と消費など、塩と日本人のつきあいを様々な視点から浮かび上がらせる名著、復刊!
目次
古代(藻塩―製塩に海藻をどう使ったか;堅塩―はたして貧者の塩であったのか ほか)
中世(中世の塩浜と塩生産者の実態はどうであったか;瀬戸内の何処で塩が作られたか ほか)
近世(近世にはすべての製塩法が出揃う;三陸海岸では海水を直接煮つめた ほか)
近代(明治維新は塩業にどのような影響を与えたか;塩田の地租改正は田畑の場合とどう違ったか ほか)
附章 塩業用語さまざま
著者等紹介
廣山堯道[ヒロヤマギョウドウ]
1925年兵庫県赤穂市に生まれる。大正大学国文学科卒業。日本歴史学会・日本塩業研究会会員。市立赤穂歴史博物館館長を務めた。2006年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。