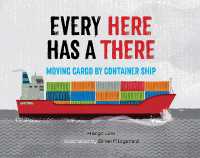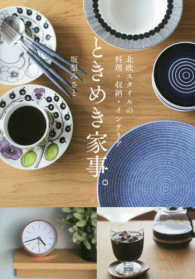内容説明
「いる」のに「いない」人間が舞台を駆け回る?本来聞こえないはずの「間」や「自然の音」までも表現。「無」に始まり「無」に終わる世界とは。歌舞伎音楽からオーケストラまで縦横に行き来する西川浩平が、日本の伝統音楽を支える「黒御簾の内側」の世界にご招待。
目次
第1章 一歩入ればそこは江戸時代?(一歩入ればそこは江戸;狂言方の姿を追って;芸能を支える日本の劇場)
第2章 黒御簾のむこう(黒御簾のむこう;黒御簾音楽は擬音の世界;四方八方縁起かつぎ;逃れられない正座のつらさ)
第3章 黒御簾古今東西(西洋の感覚と日本の感覚;落語にみる庶民の感覚;新感覚の邦楽;どの芸能にあもある約束事;崖っぷちの緊張感)
第4章 さまざまな舞台裏(邦楽器と共演するオーケストラ;ジャズと邦楽;現代邦楽の舞台裏;エクアドル公園に行ってきました!)
著者等紹介
西川浩平[ニシカワコウヘイ]
フルートを林リリ子氏に師事。第一回オーストラリア国際フルート・コンクール第三位入賞。大阪フィルハーモニー交響楽団にて活動後、現代邦楽グループ「日本音楽集団」に横笛奏者として入団し現在に至る。歌舞伎、日本舞踊公演などに従事すると共に、数々の現代曲の初演に携わる。近年は「瀬戸内寂聴訳・朗読劇・源氏物語」、日本音楽集団定期公演「和楽劇・呑気布袋(ドン・キホーテ)」、小椋桂プロデュース「アルゴミュージカル」の音楽、企画を担当するなど、分野を越えた活動を繰り広げている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Yoshihiro Yamamoto
筋書屋虫六
nrm
ふゆき
Kyoro