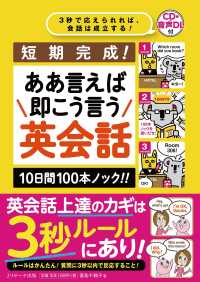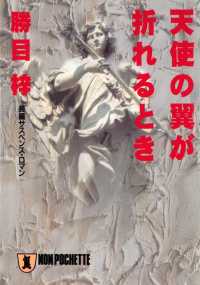内容説明
知の巨人梅棹忠夫が終生、挑み続けた登山と探検と学問。生前のロング・インタビューによる初の評伝。
目次
序章 梅棹資料室
第1章 京都―山城三十山
第2章 三高山岳部―雪よ岩よ
第3章 京都探検地理学会―最後の地図の空白部
第4章 西北研究所―モンゴル遊牧民
第5章 ヒマラヤ―マナスル登頂計画
第6章 AACK―文明の生態史観
第7章 東南アジア―カカボ・ラジ登頂計画
第8章 京大人文研究所―アフリカとヨーロッパ
第9章 日本万国博覧会―人類の進歩と調和
第10章 国立民族学博物館―比較文明学
終章 再び梅棹資料室
著者等紹介
藍野裕之[アイノヒロユキ]
1962年東京都生まれ。法政大学文学部卒業。広告制作会社、現代美術のギャラリー勤務の後、フリーの雑誌記者に。『サライ』『BE‐PAL』『山と溪谷』などの雑誌で取材と執筆に携わる。自然や民族文化などへの関心が強く、日本各地をはじめ南太平洋の島々など、旺盛に取材を重ねている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koki Miyachi
2
生態学者、民俗学者、国立民族学博物館長、そして何よりも未開の地への限りない情熱を燃やした知の巨人の評伝である。梅棹本人へのインタビューがベースになっていて、従来の梅棹本にはなかった、三髙から京大を通じて培われた探検家マインドの発露としての足跡を詳細に辿っている。より人間梅棹忠夫像が浮かび上がる良著ではないか。最初は探検との関わりがあまりに詳しすぎると感じたが、実はそこに梅棹の一番の本質があると気付いてからは、面白くて面白くて500頁もの大作をあっという間に読了した。2022/07/31
Kamimura Michiko
1
分厚かったけど中身も厚くて熱い内容でした。読み始めたらどんどん吸い寄せられていき、500ページを超える本なのに一気に読んでしまいました。一度目は早く先を読みたくて逸りながら読んでしまった感じです。生い立ちから記され、その時々の感情や考え、さらには迷いまで、著者に率直に語られています。この肉声がまた、梅棹忠夫の生身を感じさせ「会ってみたかった」と思わされました。梅棹忠夫、思いがけずひょうきんというかお茶目な人だったんだという発見。また、「知の巨人」といわれるけれど、これでもかというほどの大きな挫折を何度も経
1.3manen
0
大著ではあるが、文明の生態史観、川喜田二郎、今西錦司らの名前ぐらいは知っていたが、京都の町衆の市民社会と、モンゴルなどの世界各国の文明との比較も当然なされていたのかもしれない。そう思うと、文化人類学という学問の裾野の広さや寛大さを理解できるような気がした。2012/05/03
かりん
0
4:大作。P.457の会話は「そうかぁ…」と思わずにはいられなかった。■世界意識。もっと冷めている。東大:団、合成主義。京大:隊、養成主義。乾いた楽天性。ずっとリーダー業。組織としての使命を突きつけられたときに、それを正面から受け止め、何とかしようとするのが梅棹である。そのためには、冷徹にも情けは切り捨てる。組織の目的と個人の情熱とを両立させる。秘書はコネで決める。黒人問題の元凶をサハラに求める。銅鉄主義。不信の体系。個人対個人の接触。人間愛の発動。文明系が生態系から自由になったら。経済は二流。2011/12/09
すーさん
0
著者、藍野裕之氏が延約10年かけて梅棹忠夫氏に行ったインタビューから生まれた梅棹忠夫氏の生き様を伝えようとした著作。梅棹氏が他界してから雨後のタケノコのように出版された梅棹氏関連の書物の中でも、最も大部な作品。著者も触れていたように、梅棹氏の「行為と妄想」の焼き直しと言っては言い過ぎだが、同書と重複するところは多い。梅棹氏と対話をし者だからこそ書ける表現・エピソード等が秀逸。大部ではあるが、まだまだ書きたいことはあったと伝わる作品。2018/05/17