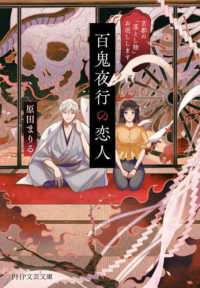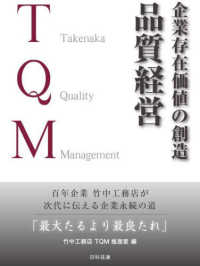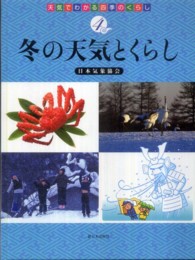内容説明
愛媛の自然に育ち、大正から昭和初期の激動の時代に青春期を過ごした畦地梅太郎は、上京後、各地の山を訪ね歩き、「山男」「生きもの」「家族」と、時代とともに作品の主題を変えながら、畦地芸術を深化させていった。畦地が本書で描くのは、畦地が敬愛する山々の自然美と山の生きものたちの姿であり、家族への愛と、故郷・愛媛の自然への憧憬である。
目次
山の果実(穂高小屋の一ととき;顔面白癬 ほか)
峠から峠へ(峠から峠へ;南土佐の山)
信濃路の回想(戸隠の回想;涸沢・上高地 ほか)
北アルプスの記(白馬大雪渓;雪渓はくたびれる ほか)
山のえくぼ(山のえくぼ;山と山の神 ほか)
著者等紹介
畦地梅太郎[アゼチウメタロウ]
1902年、愛媛県宇和島に生まれる。版画家。1920年、18歳で上京。油絵の自修期間を経て、27年、日本創作版画協会展に出品し入選、版画家への道を歩み始める。1940年ころより山を主題にした版画にとりかかり、山男シリーズなど版画作家として独自の世界を確立した。版画作品のほか、山の紀行文も数多く執筆し、多くの版画集、画文集を発表した。1999年、96歳で逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐々陽太朗(K.Tsubota)
44
文章は素朴で温かみがある。世にあるエッセイは格好をつけるというか、読者を唸らせようとするものが多いのではないか。それはエッセイストの技術であり、必ずしも悪いこととは思わないが、畦地氏の紀行文にそうしたところが感じられないのが異色だ。私が思うにやはり畦地氏は山を愛した版画家であって、文筆家ではないのだろうと。しかしそうした文章に独特の魅力がある。読んでいてこちらが構えることがなく、安心する。寝る前に2~3項目ずつ読むのが良いかもしれない。きっとおだやかな心もちでよく眠れるだろう。2025/11/04
roatsu
14
戦前から敗戦間もなく、昭和の後半あたりまで、畦地梅太郎さんが旅した山や里の紀行をまとめた一冊。戦前の長閑な四国は石鎚周辺の山村風情や峠を繋いだ山歩きの様子が興味深い。また戦後間もない白馬雪渓から祖母谷温泉、黒部峡谷を経て仙人平からの剱岳、立山一の越から五色ヶ原、三俣山荘へと続く山行は現代でもまとまった時間がなければ無理な贅沢なものでよくあの時代にと驚く。食糧、装備も山小屋も全て粗末な時代で初老の体を労わりつつ仲間と行く様子は昔の山旅がどんなものか教えてくれる。よくお腹を壊したり気の毒(笑)。その時にどうす2021/05/16
pitch
3
版画家畦地梅太郎の本二冊目。登山のエッセイと、後半は画文集。冒頭にカラーページがあって嬉しい。内容は、北アルプス縦走と、家族連れて登山行く話が面白かった。子ども4人も連れて行くのに宿の予約しないのに驚いた。当時はそれが当たり前なんだろうか。2021/04/19
-
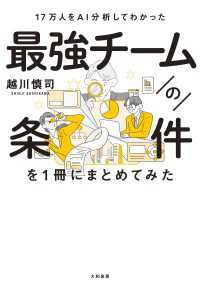
- 電子書籍
- 17万人をAI分析してわかった最強チー…